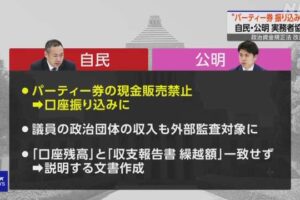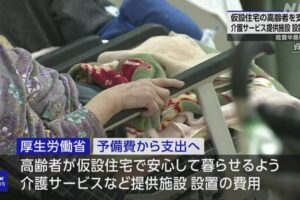東京, 2月6日, /AJMEDIA/
シュシャの高台からの下を望む。 山頂部分に位置するシュシャの街は、天然のようさい)となってきた=2022年11月10日、 国末憲人撮影
シュシャは18世紀半ば、 イランの下でこの地方に半独立国家を築いたパナ・アリ・カーンによって開かされた。 アルメニア人とアゼルバイジャン人が共存していたが、 両者は次第に対立するようになり、1920年 アルメニア人に対する迫害と追放が発生。 以後のソ連時代、 街はアゼルバイジャン人が多数を占め た。92年にアルメニア側の支配下に入ると、約1万5千人のアゼルバイジャン人住民は全員逃亡。 アルメ ニア語でシュシと呼ばれる3千人程度の田舎町になった。
到着翌朝、 シュシャ市役所の広報担当者と落ち合い、 その案内で街を回る。 城壁と絶壁に囲まれた街 シュシャは、 坂道の脇に茂る木々の緑が目に優しい。 日本で言うと山あいの温泉郷の風情だ。
この街では、アゼルバイジャンで最も著名な詩人の一人フルシドバヌ・ナタパンや、ソ連時代の著名な オペラ歌手ブルブルらが生まれた。 市役所前広場にはこうした文化人の胸像が3体並ぶ。 「これらの像 はアルメニア支配時代に破壊され、国外に売り飛ばされました。政府が見つけて買い戻したのです」
この街には、17の街路、 17の泉と、 17のモスクがあるという。 アゼルバイジャン人は一般的にイスラム 教徒で、モスクは彼らのものだ。 「まず取り組まなければならないのは、 城壁とモスクの修復です」 と、 担 当者が説明する。「17あったモスクのうち16が(アルメニア占領中に) 全壊し、一つが半壊しました。 城壁 も、アルメニア軍の砲撃で破壊されました」
モスクの一つに案内してもらう。 崩れて形をなしていない。 「どこのモスクもこんな感じです。 建物の基礎 「さえ壊されている」。 アルメニア側を非難する担当者の口調は厳しい。
では、この街にあったはずのアルメニア人のための教会はどうなったのか。 アルメニア人は一般的に キリスト教徒だ。
「修復中なので入れません」
担当者は答え、案内するのを渋った。 見るだけだと強く頼み、 何とか連れていってもらう。 広大な敷地 に立つ大聖堂の周囲に足場が組まれ、本格的な修復に入っている。 周囲を、銃を持った兵士が警備し ている。
アゼルバイジャン当局がアルメニア人の教会を修復するのは、なかなかの美談である。 なぜ積極的に広めず、 見せたがらないのか。 理由はわからないが、単に自分たちのモスクの方に関心を持ってもらいたかっただけなのかも知れない。
第2次ナゴルノ・カラバフ紛争後、 それまでシュシャに住んでいたアルメニア人は追い出されたはずだ。 「実際には、民間人はここにほとんど住んでいませんでした。 軍人とその家族ばかりだったのです」と担 当者は説明する。 しかし、 紛争前のガイドブックを見ると、アルメニア側もこの街のホテルなどを整備し、 観光客を呼び込もうとしていた節がうかがえる。
担当者には、全般的にアルメニア人の存在を過小評価する傾向がうかがえた。 ただ、対立が激しい両国の間だけに、ある程度予想できた態度ではある。
全般的に、街の荒廃ぶりは否定できない。 あちこちの建物の壁に、 大小の穴が開いている。 2年前の 「第2次紛争」の際、 銃撃戦によってできたと思われる。 被害を受けて人が住めなくなったマンションも少 なくないようだ。
一方で、 もっと以前に破壊され、 廃虚となった住居も、随所にうかがえた。 約30年前の 「第1次紛争」以 来放置されているのだろう。 一部の工事現場で人や重機がせわしなく動き回る一方で、 その他の場所に は廃屋が並び、 がらんとして人気がない。 ちぐはぐさが街に漂っている。
「普通の人」の話が聞けない
街で、 市民に話を聞こうとした。
これが、 簡単ではない。 現在この街に暮らすのは、 軍隊と警察、 建設作業員、 行政関係者らと、その 家族に限られる。 一般市民の入域は認められていない。 つまり、普通の人がいない。
ホテルの従業員に暮らしぶりを尋ねようとしたら、支配人がすっ飛んできた。 「うちの職員に取材するのはやめていただきたい」
うろうろしたあげく、 商店に買い物に来ていたアゼルバイジャン人の年配女性をつかまえることができ た。ファジラ・ゼイナロバさん。 「女性だから年齢は教えたくないね」と言う。 一般人が入れないはずのシュ シャで暮らせるのは、 息子が警察官としてここに勤務しているため、家族として滞在を認められているの だという。
シュシャ生まれ。 第1次紛争以前は、この街で幼稚園の先生をしていた。 「あそこが幼稚園だったので す」と、店先から見える建物を指す。 園児はアゼルバイジャン人で、アルメニア人の子どもたちは別の幼稚園に通っていた。
92年、アルメニア支配が始まるとともに、故郷を離れた。 「街を出た最後の1人だった」と言う
「老人やおんな子どもも構わず、 彼らはカチューシャ(ロケット砲)で撃ってきた。 だから、目に涙をためて、逃げなければならなかったのです」
それまで、アゼルバイジャン人とアルメニア人は一緒に暮らしていたはずだ。
「だから、 何が何だかわからなかった。互いに結婚している例もたくさんありましたし。たぶん、私たちとは別の第三者が入ってきて、 イデオロギーを吹き込んだのではないでしょうか」
以後、ずっと帰郷を待ち望んでいた。 亡くなった母を故郷の墓地に埋葬するのが願いだった。 街に戻っ たのは、シュシャがアゼルバイジャンの手に落ちて3週間後。 最初は電気もガスもなかったという。
ゼイナロバさんは「(アルメニア人を)許し、忘れることは難しい」と話した後で、 「許し、 忘れ、一緒に暮らすことはできると思う」とも言う。 どちらが本心だろうか。 まだ気持ちが整理できていないのかもしれない
シュシャを去る時、下界を見晴るかす場所で車を止めてもらった。 はるかかなたの平野部に、街がか すんでいる。 アルメニア側ナゴルノ・カラバフの中心地、いわゆる「ナゴルノ・カラバフ共和国」 の首都ステ パナケルトだ。 2年前の紛争では、 アゼルバイジャン軍のミサイル攻撃を受けて大きな被害を出した。
ステパナケルトとその周辺の住民はほとんどアルメニア人で、 アルメニア側が実効支配している。 そこには第2次紛争以来、 平和維持部隊としてロシア軍が駐留する
アルメニア側とアゼルバイジャン側との境界を隔てるのは、ごく簡便なフェンス1枚に過ぎない。 ただ、 それは本来、超えられる人のいない厚い壁のはずだった。
筆者が訪ねた翌月にあたる昨年12月、このフェンスを越えて、アゼルバイジャンの自称環境団体がア ルメニア側になだれ込む事件が起きた。 団体はステパナケルトとアルメニア本土を結ぶ唯一の道路を封鎖。 食料や医薬品が入らなくなったステパナケルトでは、人道危機が騒がれる事態に陥った。 アルメ ニアはこの行為を「ジェノサイド (集団殺害)に向けた準備だ」と非難した。 封鎖は、年を越えて2023年1 月に入っても続いている。
今回の取材は、アゼルバイジャン政府に出した要請が認められて実現した。 ナゴルノカラバフとその 周辺の奪還地域での取材は、フランスのラジオ記者とともに行動するツアーで、行程の大部分に政府関 係者が同行した。 明確な取材規制はなかったが、時間の制約もあり、取材対象は限られた。 奪還地域以外の村や首都バクーでの取材に制約はなかった。 (シュシャ=国末憲人 )
続きがある