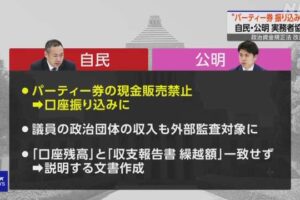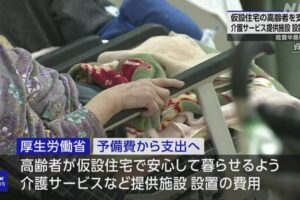東京, 9月4日, /AJMEDIA/
未承認国家というあまり知られていない現象を視野に置くことで、2022年のロシアとウクライナをめぐる情勢がどのように見えてくるのか、その景観を廣瀬さんに教えてもらってきた。
ここで、少し翻って、廣瀬さんがなぜ、このように深く、旧ソ連諸国に関心を抱くようになったのか聞いておきたい。
そのような質問をすると、廣瀬さんは、「思い切り振り返りますと──」と小中学生だった頃の話から聞かせてくれた。
「もとはと言えば、技術指導で祖父がソ連に長期出張していたことがあると思います。祖父から聞くソ連の姿は、とにかく日本しか知らなかったわたしにとって、異質なものでした。現地ではずっと見張りがついて、ホテルでも監視されるし、日曜日もずっとKGBがくっついてくるから、動物園にでも行くしかなかったとか。レニングラード(現在のサンクトペテルブルク)に行きたいと思って何度も申請を出したが通らなかったとか。食べ物がヨーグルトとふかしたジャガイモしかないんだよとか。外国人や特権階級向けの『べリョースカ』というスーパーマーケットがあるとか……。あんな国行くなよ、といつも言われていましたが、わたしには面白く感じられていた部分もあったのですよね」
ソ連時代にロシアやソ連の他の共和国を訪ねたことがある人は、今となっては貴重な経験をしていたのだとこの話を聞いて思い出した。
ぼくは1991年にソ連が解体する直前、90年から91年にかけて何回かモスクワ、カザフスタン、さらには極東地域のナホトカ、ウラジオストクなどを立て続けに取材の仕事で訪ねる機会があったのだけれど、その際の経験は廣瀬さんのお祖父さんと似たものだったと思う。ホテルには監視がついているし、自室で日本語で会話したことが、なぜか現地ガイドに知られていてびっくりしたこともあった(盗聴しているのだから、不用意なことは言わず、厄介事を増やすなという忠告だったと理解している)。組織がきわめて中央集権的かつ場当たり的で、できると言われていた取材に出かけても、その場で、理由の説明もなく「取材はできない」と断られることも多かった。外国人が「人と人」の付き合いをすることが難しく、相手がしばしばなにか別の大きなものに動かされている瞬間を目撃することにもなった。嫌な瞬間もたくさんあったけれど、話題の尽きない「面白い国」ではあった。
さて、多感な時代にそのような話を聞いていた廣瀬さんが中学生の頃、ソ連をめぐる大きなうねりがおきる。
「ソ連で、ゴルバチョフ政権が誕生して、ペレストロイカが始まって、衝撃を受けました。1987年には、コルバチョフ書記長と米国のレーガン大統領の間で、中距離核戦力(IMF)全廃条約も署名されて、核の世界も変わると思い、期待が大きく膨らみました。これは歴史に残る、すごく大きなことなんじゃないかと思ったのです。あと衝撃的だったのは、やっぱり1989年のベルリンの壁崩壊と東欧革命ですね。これが1カ国じゃなく、民主化ドミノという形で旧ソ連内でどんどん続けて起こっていったのはすごく衝撃的で、連鎖するのが興味深いと思いました」
廣瀬さんの進路を決めるにあたっての大きな助言が、その時にあった。
「母が、大学は偏差値で選ぶのではなくて、やりたいことができるところを選ばなきゃだめだと言うので、じゃあ、わたしにとっては何だろうと考えたんです。それで、東欧革命が連鎖的に次々起きることが面白いと感じたことを思い出して、じゃあ、そういうことをどこで学べるんだろうと調べました。すると、東大のような大きな大学でも学べそうになかったんです。政治も絡むし、経済も絡むし、もういろんなことが絡んでくる。そこで目をつけたのがSFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)でした。社会変動を扱う先生もいらっしゃいましたし、地政学や国際政治も経済も学べるし、ここしかないと思って、AO入試を受け、合格をいただきました。そのため、ここしか大学を受けてないんです」
まだ今のようなインターネット環境もない中で、どの大学にはどんな先生がいて何を研究しているのかというところまで調べた上で、廣瀬さんは受験校を決めた。また、当時はAO入試の草創期で、今のようにAO入試向けの学習塾などがない中、「素のまま」で難関を突破したことになる。
「それで、SFCに通った初めての日に、『ゴルバチョフ、日本の学生と語る会』に行きたい人は応募しなさいというようなポスターが貼ってあるのを見つけたんです。『おー』と思って、締め切りが翌日だったんですけど、頑張って書いたら選ばれたんですよ。そのとき来日したゴルバチョフ大統領はものすごくオーラがあって輝いて見えて。ああ、かっこいい! と思って。やっぱり、こういう人が国を変えるのよね、と思っていたのですが、それから4カ月もたたずに、いわゆる『8月クーデター』(1991年)が起きて、ゴルバチョフの権威は地に落ち、ソ連が解体していくのです。わたしは何か放心状態になってしまい、いったん旧ソ連に対する関心を失ってしまいました」
次に廣瀬さんが、ソ連、いや、ソ連解体後の、旧ソ連国家群に関心を持つのは、東京大学の大学院に進学した後のことだ。
「最初、国際公務員になろうと思っていたんですよ。なので、SFCの大学院に行って留学しようと考えていたんですけど、当時SFCの先生方が、きみは研究者に向いているので研究のできる大学院に行きなさいと薦めてくださるので、東京大学大学院の法学政治学研究科の研究者養成コースを受験したんです。自分としては賭けで、そのコースはほとんど内部進学生しか取らないような狭き門と聞いていたので、もしも受かったらきっと本当に研究者に向いているということなのだろうと思って。そして、実際に受かって、国際政治の理論をやろうと思ったのですが、指導教員のうちのお一人が、理論をやっていても結局机上の空論になるので、地域を持ちなさいとご指導くださり、では、どの地域かとなった時に、やはり旧ソ連しかないと思ったのです」
ここで、廣瀬さんは「ロシア研究」を志したのだと思う人も多いかもしれない。ぼくも最初、そう思った。しかし、廣瀬さんは、その点について強いこだわりを持っている。
「旧ソ連とロシアはイコールではありません。ロシアにはロシアのアイデンティティがあるわけで、ロシア人はロシア=ソ連って思われるのが嫌なんですよね。ロシア以外の旧ソ連国家も同様で、『ロシア』とは別の国家、アイデンティティを持っていますので、ロシアと同一視されることは好みません。わたしは、そこにはこだわりがあって、自分の紹介をされるとき、専門をロシア研究とされることが多いんですけど、変更していただける場合は『旧ソ連研究』にしていただいています。ロシアだけじゃなく、旧ソ連を全部見るという視点が重要だとも思っているので」
ここから先は、すでに語ったことと、かなり重なってくる。修士論文(ベトナム戦争に旧ソ連がどう関わったについてのもの)を仕上げた後、さらに踏み込んだ研究をするために選んだのがアゼルバイジャンへの留学だった。未承認国家というロシアに都合よく利用されている現象も含めて、日本で入手できる情報は限定的なので、とにかく現地に行くしかない、と。
「未承認国家にしても、紛争にしても、いろいろあるわけですし、それぞれ性格が違っているので、どこを選ぶかは相当迷いました。それによって自分の最初の一歩は大きく変わってくるなと思いましたし。結果、アゼルバイジャンの首都バクーを拠点にして、その期間にジョージアにもアルメニアにも行きました。先に当時のバクーの印象が真っ黒だったという話をしましたけど、あの頃のジョージアも、厳寒期の首都トビリシですら、夜の数時間しか通電しないほど計画停電がひどく、かなり厳しい状況でした」
ちなみに、アゼルバイジャンで暮らし始めて、廣瀬さんは高校生の時の自分が熱中した、ゴルバチョフ元大統領の評判がきわめて悪いことを、今更ながら痛感することになる。これは、日本にいると「ペレストロイカを推し進めた功績はあるものの、結果的に国家運営に失敗しソ連の崩壊を招いた」という相反する評価が耳に入ってくると思うのだが、旧ソ連で聞くゴルバチョフ評は、最悪と言ってよいほどに悪いという。
「昔、ゴルバチョフが好きでした、とは一言も言えなくなりました。『最初はよかったけれど、後で国家運営に失敗した』ということではなくて、最初から評判悪いですし、それも特にアゼルバイジャンだけというわけでもないんです。ゴルバチョフ時代にソ連の各地で、反ロシア的な行動が起きたとき、彼は激しい弾圧をしていたんですよね。アゼルバイジャンの場合ですと、1990年、ソビエト連邦軍がバクーに侵攻した『黒い1月事件』があり、相当数の一般人が殺されました。それを決断したのは、最後はゴルバチョフです。わたしが、『ゴルバチョフすごい』と思っていた頃は日本では相当なアンテナを張っていない限り、そういう情報はキャッチできなかったと思います。しかし、後で調べてみると、旧ソ連のあちこちで弾圧や流血の惨事が起きていたんです」
「黒い1月事件」があった1990年は、廣瀬さんが大学に入学した前年であり、廣瀬さんが会ったゴルバチョフ大統領は、そういった弾圧をすでに行った後だったのである。
「というわけで、旧ソ連の人から見ると、外面ばかりよくて、ノーベル平和賞をもらったりして、外国ではもてはやされているけれど、国内では残酷な流血の惨事を何度も起こしてきたひどい人間だということで、ゴルバチョフへの見方はとても厳しいです。しかも、旧ソ連で弾圧をしていたゴルバチョフに対する欧米の反応は、あくまでゴルバチョフに同情的だったって、みんな言っていました。そして、結局、国家運営にも失敗し、大国ソ連を葬ってしまった『墓掘り人』じゃないかという、恨みつらみしかないんですよね。そういうこともあって、もう調べれば調べるほど、旧ソ連の人々のソ連、自分の生まれ育った民族共和国、ゴルバチョフなどへのさまざまな感情が実に複雑なんだということがわかりました」
これは研究者として立った廣瀬さんが、かつての自分のアイドルが地に墜ちたことを受け止め、旧ソ連というまとまりを理解していくにあたっての最初の一歩のところで起きたことだ。日本に伝わってくる情報だけでは、本当に一面しかわからないことがあるという事例でもあった。
「それで、ナゴルノ・カラバフ紛争も、調べれば調べるほど、様々な陰謀説のような怪しい話が多数出てきて、紛争自体、KGBがあえて憎悪をあおるような形で引き起こしたのではないかという説すらあります。すでにお話ししたスムガイト事件の後にも、多くの虐殺事件などが起きるんですけど、それらにはほぼ必ず陰謀説がくっついているんですよね。現地住民が真顔で話すストーリーは仮にそれが陰謀説だったとしても、極めて重く突き刺さってきますので、わたし自身が混乱しそうになったことは数え切れません」
ジャーナリストなら、「何が真実か」なのかを探究するのが仕事になる。研究者も、当然、実際に起きたことを正しく理解することを目指す。しかし、それと同時に「信じられていること」がどのように世界を動かすかに着目しなければならないことも多い。この地域をテーマにした廣瀬さんの研究が、未承認国家という、国際的には認められなくとも、その場にいる人たちには現実であり、実体である「国家のようなもの」、そして、虚/実、正規/非正規を織り交ぜたハイブリッド戦争といったテーマに沿って展開していったのは、まさに必然だったように思える。
さて、21世紀の最初の20年ほどの間、廣瀬さんが積み上げてきた研究の片鱗については、すでに語っていただいたので、あらためて2022年2月、ロシアによるウクライナ侵攻が始まる前後の話に戻ろう。
あの「2月24日」の衝撃からある程度の時間がたった今、当初の茫然自失から立ち直って、顧みた時、どんなことが言えるだろうか。そもそも、廣瀬さんはなぜ、侵攻を「ありえない」と考えていたのだろうか。
「政治的整合性が全くないんですよね。全く論理的にメリットがないことであって、それをやることによって何の得もないわけですよ。どう考えても。そんなことをまさか政治家が行うのかというところに非常に大きな疑問を感じていました。未承認国家についても、これは旧ソ連の中で反ロシア的な国を制御するのに非常に便利な存在であって、ロシアはそれを持っておくと外交カードとして得なんですよね。それなのに、『ドネツク人民共和国』と『ルガンスク人民共和国』を国家承認してしまっては、もう未承認国家として使えなくなってしまいます。それをやってしまった2月21日の段階で、侵攻は不可避となっていたと言えます。逆に言えば、侵攻の準備として国家承認を行ったと言えます。そもそも、2月24日の侵攻を宣言するプーチン大統領の演説で、プーチンはウクライナ東部2州がロシアに助けを求めてきたのを受け、『国連憲章第7章51条と、ロシア安全保障会議の承認に基づき、また、本年2月22日に連邦議会が批准した、『ドネツク人民共和国』と『ルガンスク人民共和国』との友好および協力に関する条約を履行するため、特別な軍事作戦を実施する決定を下した』と述べているんですよね」
国連憲章第7章51条とは、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」という内容で、加盟国による個別的・集団的自衛権の行使を認めるものだ。つまり、ロシアの論理に基づけば、ロシアが国家承認をした主権国家たるドネツク・ルガンスク両「人民共和国」から軍事支援を要請されたので、「両国」承認の際に締結した条約に基づき、集団的自衛権を行使して侵攻に踏み切ったということになる。ロシアにとって、ウクライナ侵攻は、国連憲章と条約に基づいた行動なのである!
ただし、なぜロシアが、あるいはプーチン大統領が、このような大きな構えで事を起こしたのかということには謎が多い。国連憲章を持ち出さなくとも、条約を理由にせずとも、ロシアは侵攻できたはずだからだ。
「ジョージアのアブハジア、南オセチアと同じように、ドネツク・ルガンスク両『人民共和国』では、すでにロシアパスポートをかなり配布していましたし、また、ロシアはそもそも外国に在住するロシア人やロシア語話者を『自国民』とみなしてきた経緯から、両『人民共和国』に対して個別的自衛権を行使して『自国民保護』のためにウクライナに侵攻し、それを正当化することも可能だったはずです。いずれにせよ、国際的に受け入れられる論理ではありませんが」
本当になぜ、この時、このような動きになったのか、今から振り返ってもミステリアスだと言える。
廣瀬さんがこれまで観察し、理論構築していたロシアと旧ソ連諸国の関係は、ある時期、ある局面を適切に切り取って描写し得ていたかもしれないが、「2022年2月24日」は、その景観が一気に変わった瞬間だった。だから、廣瀬さんは、「私は重要な研究対象の一つを失い、これまでの研究人生で構築してきたセオリーは水泡と化した」と大学ウェブサイトの記事に書いた。しかし、正確には、研究対象が変質したために、これまでのセオリーを根本的に見直さなければならなくなった、ということだろう。
「パラダイム・シフトが起きている、というふうに感じています。たとえば、直近だと『冷戦の崩壊』というのが、大きなパラダイム・シフトの時代だったと思います。今さらに、『冷戦後』つまり、ポスト・冷戦時代が終わろうとしているのでしょう。以前とは異なる新しいパワーバランスが出てくるのは間違いないかと思っています」
ならば、従来の秩序が崩れた後で、どんな秩序が現れるのだろう。それは、まさに現在進行形の「ロシアによるウクライナ侵攻」を受けてのことになるわけで、わたしたちは秩序の再編の瞬間に立ち会っている。そして、廣瀬さんは、ニュースで報じられるような戦況ばかりではなく、周辺の旧ソ連国も含めた動きを見つつ、思考をめぐらせているのである。