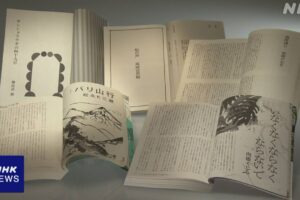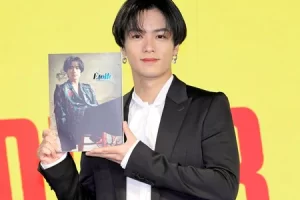東京, 6月8日 /AJMEDIA/
年末に聞こえてくる「第九」。
ドイツの作曲家、ベートーベンが作曲した交響曲第9番の第4楽章にあるドイツ語の合唱部分は、おそらく誰もが一度は耳にしたことがあるだろう。
ことしは第九のウィーンでの初演から200年の世界的なメモリアルイヤーとなっている。
では、あのなじみの深い旋律に次のような歌詞がつけられていたことはご存じだろうか。
「今日しも擧(あ)げます かしこき御典(みのり) 祝へ祝へ今日のよき日…」
実はこの歌詞は、今から100年前に福岡県で日本人が初めて第九の一部を演奏したときのものだ。
100年、200年と時を越えて歌い継がれる第九。日本ではどのように演奏され、伝えられてきたのか。その歴史をひもといていく。
(科学文化部 堀川雄太郎)
日本と第九の始まりを求め徳島・鳴門へ
ベートーベンの第九と日本の最初の出会い。
その舞台は徳島県鳴門市にある。
ことし5月、市内で演奏会が開かれた日にあわせて現地を訪れた。
第九を歌うために開かれるこの催しは、ことしで40回目を迎える。
約850人の観客が見守る中、オーケストラとともに舞台に立ったのは、250人近くの大合唱団だ。
地元に限らず、北海道や沖縄、それにアメリカや中国から、日ごろ第九を歌っている有志が駆けつけた。
オーケストラの演奏、そして4人のソリストとともに、合唱団が迫力ある「歓喜の歌」を披露すると、客席からは立ち上がって拍手をする人の姿も多く見られた。