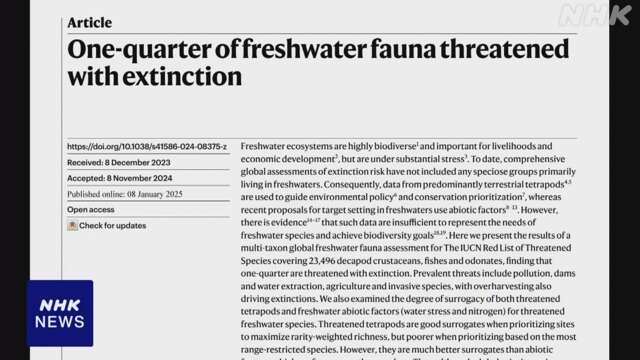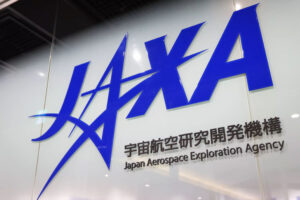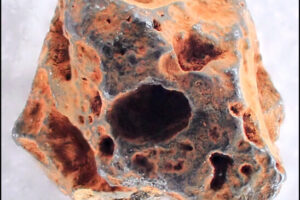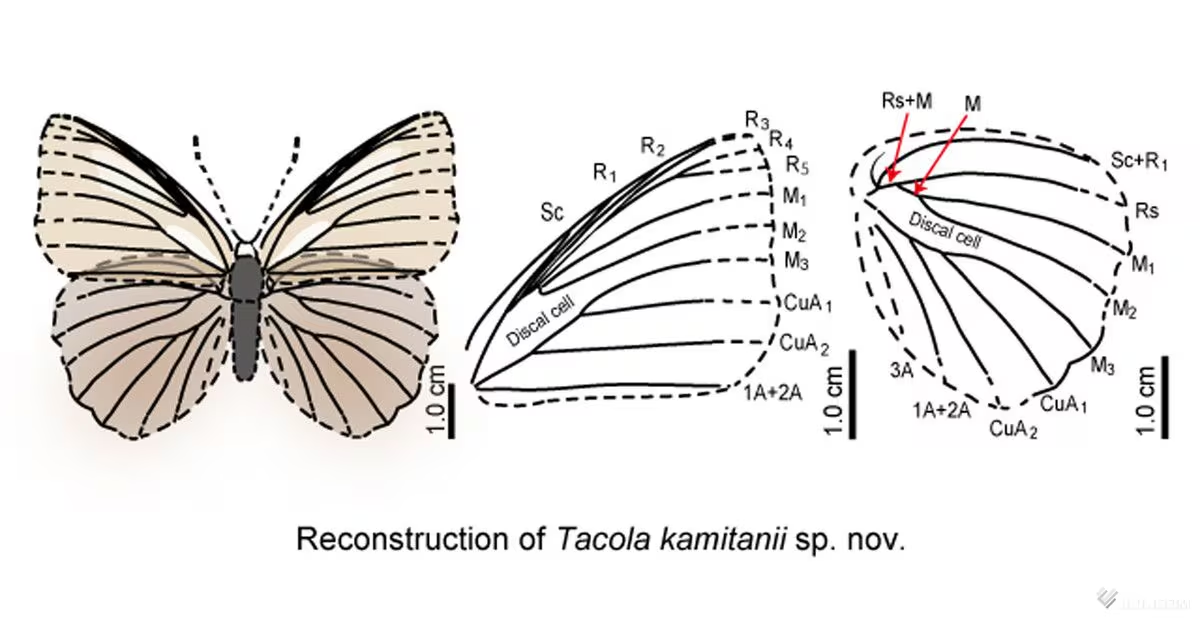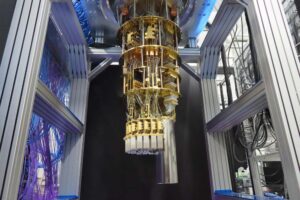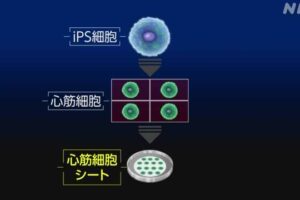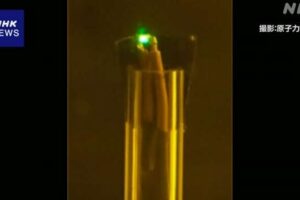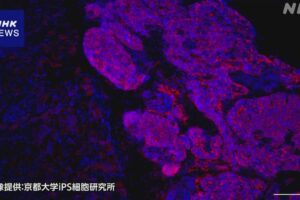東京, 1月18日, /AJMEDIA/
世界の川や湖、湿地などの淡水に生息する魚やザリガニなどの生物、およそ2万3000種のうち24%が絶滅の危機にあるという分析結果を、IUCN=国際自然保護連合の研究チームが発表しました。日本固有の淡水魚のおよそ40%も絶滅の危機にあると分析され、専門家は、早急な対応が必要だと指摘しています。
世界の野生生物の専門家などでつくる、IUCN=国際自然保護連合の研究チームは、20年以上かけて世界の淡水生物2万3496種の生息状況を分析し、今回、その結果を発表しました。
それによりますと全体の24%が絶滅の危機にあるということです。
具体的にはザリガニやカニ、エビなどの甲殻類のグループは30%が、淡水魚については26%が絶滅の危機にあるとしていて、農業や都市の排水による水質の汚染やダムの建設、それに気候変動などが影響しているということです。
一方、今回の分析に関わった京都大学大学院の渡辺勝敏教授によりますと、日本国内ではアユモドキやミヤコタナゴなど、日本固有の淡水魚のうちおよそ40%が絶滅の危機にあると分析されたということです。
水田の周辺などの生息地の減少やブラックバスなどの侵略的外来種の増加が影響しているということで、渡辺教授は「日本の状況は世界に比べても深刻だ。絶滅を防ぐために水辺の環境保全や外来種を広げないことなど社会全体で早急に対応する必要がある」と指摘しています。
世界の生き物の10%は淡水に生息すると言われていますが、淡水生物の絶滅リスクについて世界的な規模で分析が行われたのは、初めてだということです。