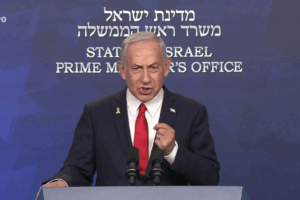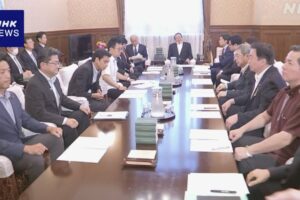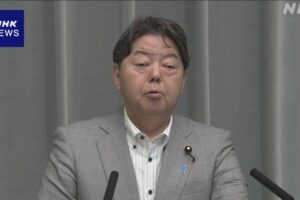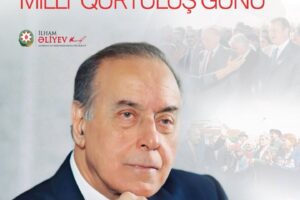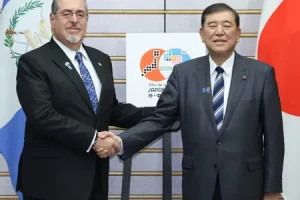東京, 10月20日, /AJMEDIA/
安全保障関連3文書改定の与党協議は、「反撃能力(敵基地攻撃能力)」の在り方が最大の焦点だ。北朝鮮の弾道ミサイル発射などを踏まえ、自民党は抑止力を高めるために保有に積極的。一方、公明党は「先制攻撃」とならないよう厳格な歯止めをかけるよう求めており、自公の主張には隔たりがある。
反撃能力は、敵のミサイル発射拠点を直接たたく能力のこと。憲法は専守防衛を定めているが、一定条件下では自衛の措置として認められるというのが政府見解だ。1956年の鳩山一郎首相(当時)の「他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能」との国会答弁を根拠としている。
仮に反撃能力を行使する場合、敵が攻撃に着手したと認定する必要がある。着手前の攻撃は憲法や国際法が禁じる先制攻撃となるからだ。
石破茂防衛庁長官(当時)は2003年の国会答弁で「『東京を火の海にするぞ』と言ってミサイルを屹立(きつりつ)させ、燃料を注入し始め、不可逆的になった場合は一種の着手だ」と例示。敵の攻撃で被害が発生する前でも着手と認められるとした。
自民党は反撃能力の保有に向け、射程1000キロ超のスタンド・オフ・ミサイルなど必要な装備品を整備すべきだと訴えている。
これに対し、着手の厳格な運用を求める公明党は「敵の攻撃後」と主張する。北側一雄副代表は9月1日の会見で「武力攻撃がなされ、反撃として必要最小限の対処を行っていく大前提の下で議論は進めないといけない」と自民党をけん制した。
ただ、着手の厳格化は相手に手の内をさらすことにつながり、「有事の際に柔軟な運用ができなくなる」(国防族中堅)との懸念がある。このため自民党はできる限り曖昧にしたい意向だ。
攻撃の範囲をめぐっても自公の溝は深い。自民党が司令部など「指揮統制機能」も対象とするよう求めているのに対し、公明党は消極的で「必要最小限の範囲内」との立場だ。
そもそも北朝鮮のミサイル発射は、事前にその兆候を把握しにくい潜水艦や移動式発射台(TEL)など多様化しており、「着手のタイミングを見極めるのは困難」(防衛省幹部)との見方もある。与党協議では、反撃能力の保有が現実的な防衛力強化につながるかも議論となりそうだ。
◇反撃能力に関する主な政府答弁
鳩山一郎首相(代読) 1956年2月
「わが国土に対し、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられない。そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾などによる攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であると思う」
野呂田芳成防衛庁長官 1999年8月
「他に手段が無い場合に敵基地を直接攻撃するための必要最小限度の能力を保持することは法理上も許される。憲法上、その保持が許される自衛のための必要最小限度の能力を保有することは専守防衛に反するものではない」
石破茂防衛庁長官 2003年5月
「わが国に対する急迫不正の武力攻撃があることというのは、被害があってからではない。『東京を火の海にするぞ』と言ってミサイルを屹立(きつりつ)させ、燃料を注入し始め、それが不可逆的になった場合というようなのは、一種の着手であり、不可逆的な状態だ」
※肩書はいずれも当時。