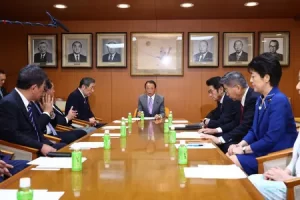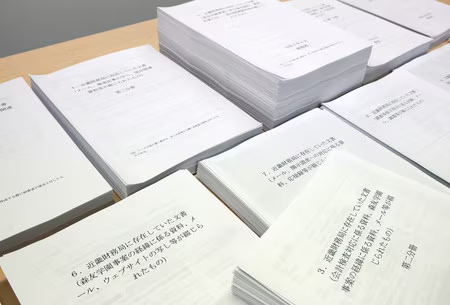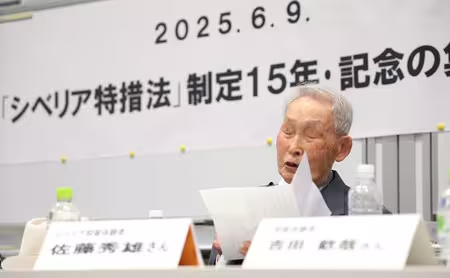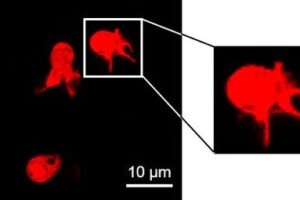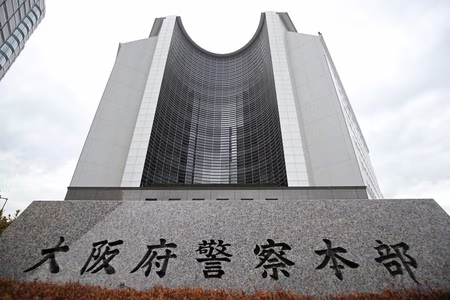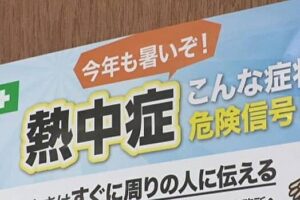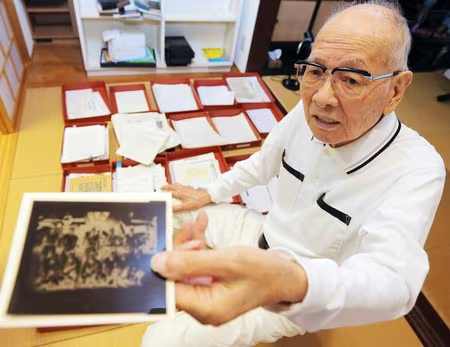東京, 10月1日, /AJMEDIA/
日本海溝・千島海溝地震の津波対策を強化する地域が決まり、指定自治体はハード整備などを本格化させる。ただ、財政支援があっても小規模市町村にはなお負担が大きい。防寒対策も求められる中、被害軽減に向けた検討は緒に就いたばかりだ。
北海道浜中町の中心部は地震発生後28分で1メートル浸水すると想定され、10分以内に避難を始める必要がある。高台に逃げるのに時間がかかる地域もあり、町は津波避難タワーの整備を検討。特別強化地域の指定で国の財政支援が拡充され、町の負担は2分の1から3分の1に減る。
同町担当者は歓迎しつつ「それでも小さい自治体には負担が大きい」とし、道の独自支援に期待する。道は防災対策の全体像となる推進計画を作り、市町村に基本方針を示す考えだが、道担当者は「市町村のハード整備の規模感がまだ分からない。何ができるか検討はこれからだ」と話す。
強化地域の指定が住民の防災意識を高めるきっかけになると考える自治体もある。北海道八雲町の担当者は、ハードに頼ると費用が膨大になるため「ハザードマップの周知や訓練の充実などソフト対策にも力を入れていきたい」と強調する。
避難路や避難場所の雪・防寒対策も急がれる。北海道広尾町では町南部の津波避難場所に続く階段に雪が積もらないよう屋根を付けている。担当者は「補助引き上げを活用し、他の避難階段にも付けていきたい」と話す。
宮城県石巻市では、居室付きの避難タワーを市内に4カ所整備。いずれも214人を収容できる規模だ。ただ、地震の揺れや津波による火災を避けるため、ガスや灯油を使う暖房器具は置けない。現在、毛布や防寒シートを備蓄しているが、さらなる準備を検討する。
一方で、道内のある自治体の担当者は「正直、どんな対策があるか分からない。アイデアを出すには限界がある」と漏らす。道内は氷点下20度に達することもあるが、防災担当の職員やノウハウも限られ、この担当者は「道や国が広い視点で対策のリーダーシップを取ってほしい」と求める。