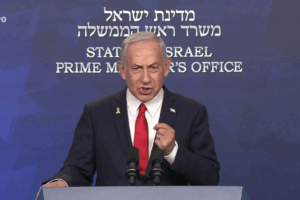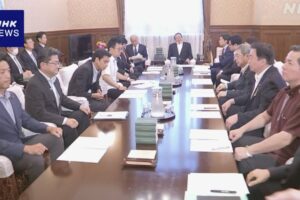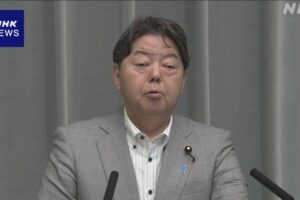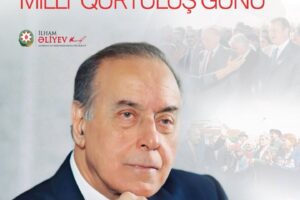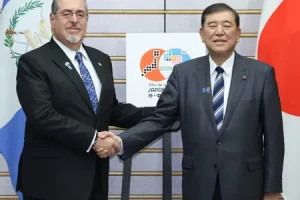東京, 10月25日, /AJMEDIA/
10月6日、国際連合人権理事会において、米、英、カナダなどの西側諸国が、新疆ウイグル自治区(以下「新疆ウイグル」)におけるウイグル人の人権状況に関し討論を行う議案を提出したが、反対19票、賛成17票、棄権11票で否決された。
その内、棄権票を投じたイスラム諸国はマレーシア、リビア、ガンビアであり、反対票を投じたのはパキスタン、インドネシア、アラブ首長国連邦、カタール、スーダン、セネガルだった。同じイスラム教を信仰するウイグル人の人権問題について、討論を支持するイスラム諸国は1つもなかった。
しかし、討論しないからといって、問題が存在しないわけではない。新疆ウイグルを巡る問題は一般的に知られている以上に長期的な問題である。これからも存在し続ける問題というだけでなく、実はかなり前から起こっている問題なのだ。
新疆ウイグルを巡る問題はいつから存在するか?
歴史をさかのぼると新疆ウイグルは、中国文化と西アジアおよび地中海文化が交流する「シルクロード」の重要な拠点であった。現在、新疆ウイグルに住むウイグル人は唐代(7世紀)には「回鶻(かいこつ)」と呼ばれ、元代(13世紀)より一般的にイスラム教を信仰するようになった。
彼らが使用するウイグル語は、ウズベキスタン、キルギス、アゼルバイジャン、トルコなどの国家と同じ「テュルク語(チュルク語)」に属する。
例えば、新疆ウイグルの首都ウルムチから、東の北京に向かって一本、西のイスタンブールに向かって一本線を引くとするなら、イスタンブールへ伸びた線上ではウイグル人は自身の民族言語で意思疎通ができる。一方で、北京へ伸びた線上では、中国語が話せないと会話は難しい。
歴史上、漢代、唐代および元代の時代は、漢族などが新疆ウイグルの一部地域を統治していた。現在の中国地図に「新疆省」として表示されている地域は、清代に絶えず起きた戦争によって得られたとされるものだ。
20世紀初頭、民族国家の流れが勃興し、第1次世界大戦後、ヨーロッパにおいてポーランド、チェコスロバキア、オーストリア、ハンガリー、フィンランド、リトアニアなどの新しい国家が誕生した。
この民族国家勃興の流れに、世界の他の地域も大きく影響を受けた。その典型的な例として、トルコが挙げられる。トルコは、オスマン帝国最後の君主(スルタン)を追放し、イスラム帝国の継承人という身分を捨て、西側諸国式の民族国家となるよう転換した。トルコ共和国初代大統領ケマル氏の非常に大胆かつ全面的な政策によって、トルコの女性は1934年には選挙権を得た。これはフランスやスイスといったヨーロッパ諸国の国々よりも早い。
トルコの変革の影響は、遠く離れた新疆ウイグルにまで波及した。一部の人々は、オスマン帝国の消滅を惜しみ、国を超えてイスラム民族として団結し、西側諸国に立ち向かおうと主張する「汎イスラム主義」を唱えた。その一方で、19世紀初頭に提唱された、テュルク語を使用する、ウイグル人も含むテュルク民族で1つの国家を形成しようと主張する「汎テュルク主義」も、ウイグル人に大きな影響を及ぼしていた。そして、トルコを見習ってウイグル人独自の民族国家を作ろうという人々も現れた。
この3つの主義の主張はそれぞれ全く異なり、ウイグル人内部でも分裂している。いずれにせよ、これら主義を実現するには1つの大前提があることは疑いの余地もない。それは、漢族が主体となる中国の統治から抜け出すことだ。
ソ連の支持と「東トルキスタン共和国」成立
新疆ウイグルの独立運動は、トルコ、イギリス、そしてソ連の支持を受けた。特にソ連は、新疆ウイグルがモンゴルのように中国から抜け出し、実質上、ソ連が掌握できる範囲下に収まってくれることを願っていた。そのため、ソ連は、中華民国政府との関係が悪い新疆の軍閥を率いる盛世才(漢族)を長い間支持していた。ところが、盛世才は中華民国政府との関係を好転した。
その後も、ソ連はウイグル人による武装闘争を支持する。1944年11月初頭、赤軍を率いたソ連軍将校が新疆に派遣され、ソ連派のウイグル人と落ち合い、新疆のイリ、タルバガタイ、アルタイの3地区を占領して「東トルキスタン共和国」を成立させた。翌年1月15日には、中華民国から脱却し独立宣言をしている。
その後、中華民国の政府軍は、東トルキスタン共和国のソ連人およびウイグル人の連合軍と絶えず交戦した。当時、第2次世界大戦も最終段階で、1945年、名義上同盟国であったソ連と中華民国は「中ソ友好同盟条約」を締結し、ソ連は表向き「東トルキスタン共和国」の名称を撤廃することに同意した。しかし、実際は、それまでと変わらずウイグル人に絶えず武器を提供し続けた。
その後、中国国内で内戦が勃発し、誰もが予想しない事態が起こる。ソ連からの手厚い援助と支持を受けた中国共産党が国民党を打ち負かし、中国の統治者となったのだ。ソ連からしてみると、中国全てがソ連の勢力下に収まったと言える。このため、新疆ウイグルの独立運動を推し進める理由はなくなった。
中国共産党統治下の新疆ウイグル
1949年から中国共産党が中国を統治し、新疆ウイグルも他の中国の地域と同様、中国共産党主義によるおとぎ話のようなプロパガンダと狂気じみた政治運動に飲み込まれることとなる。独立のムードもほぼ消え失せた。
80年代に入り、鄧小平が改革開放を推し進め、中国の経済は大きな飛躍を遂げたが、一方で不公平な富の分配が社会問題となった。この問題は、いわゆる少数民族の身においてとりわけ突出していた。
表面上、中国共産党政権は少数民族に対して優遇政策を講じていた。例えば、一人っ子政策において、漢族は1人しか子供を産めなかったが、少数民族は2人、またはそれ以上子供を産んでもよかった(少数民族それぞれの人口によって、子供の数は決められていた)。
しかし、中国共産党の経済発展は、腐敗社会の上に成り立っており、政府要員が資源と権力を掌握している。彼らは資源や権力を自身の親戚や友人に移譲し、その者たちによって会社が経営され富を生む。これが中国の基本的な経済分配モデルである。このような政府要員は大部分が漢族で占められ、富はコネクションの分配を経て、最終的にやはり漢族に分配される。ウイグル人に限らず、いかなる少数民族もこの分配構造では端へと追いやられる。私自身、いわゆる少数民族なので、これは私が身をもって体験した疑いようのない事実である。