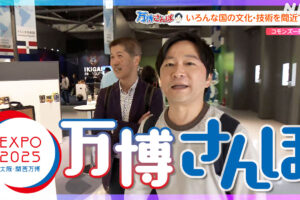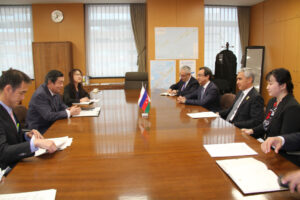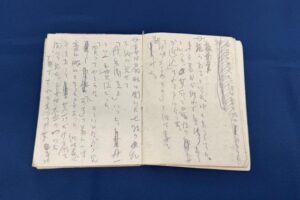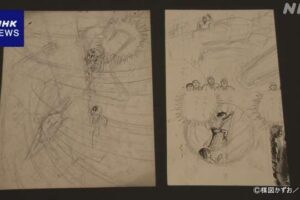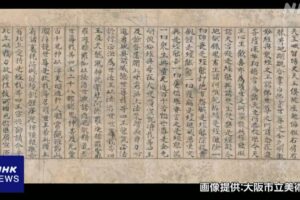東京, 3月2日, /AJMEDIA/
古都 奈良に春の訪れを告げる東大寺の伝統行事「修二会」(しゅにえ)の一環で、二月堂の舞台から大きなたいまつを振って火の粉を散らす「お松明」が1日から始まりました。
「お水取り」の名で知られる東大寺二月堂の「修二会」は、国の安泰などを願って11人の僧侶たちがおよそ1か月にわたって法要などを行う、奈良時代から続く行事です。
1日から「お松明」が始まり、「童子」と呼ばれる僧侶の補佐役が燃えさかるたいまつを二月堂の欄干から突き出して駆け抜けると、暗闇のなか、火の粉が勢いよく降り注ぎました。
1日はあいにくの雨となりましたが、訪れた人たちは傘を差しながら静かに幻想的な光景を見守っていました。
奈良市の20代の男性は「初めて見ましたが、思った以上に迫力があって感動しました。来年もまた来たいなと思いました」と話していました。
「お松明」は今月14日までの日程で毎晩行われますが、寺は新型コロナウイルス対策として12日については非公開とし、ほかの日程についても二月堂周辺の立ち入り人数を制限することにしています。