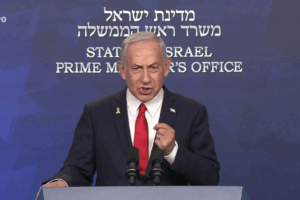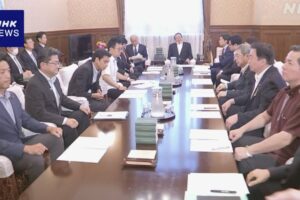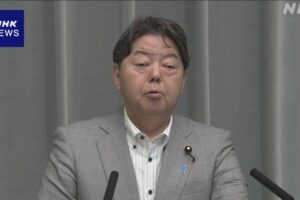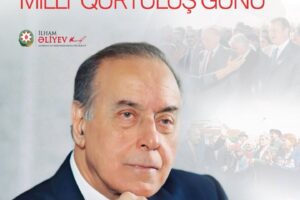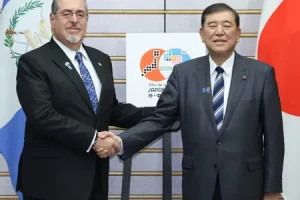東京, 8月29日, /AJMEDIA/
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)のメディアセンター所長/総合政策学部教授である廣瀬陽子さんは、今年4月、つまり、年度のはじめの時期に、大学ウェブサイトの「おかしら日記」記事の冒頭で、そう書いた。
2022年2月24日とは、ロシアがウクライナに対する「特別軍事作戦」を宣言し、侵攻を開始した日である。日本に住む多くの人々は、その件を、2月24日の朝、新聞、テレビ、ネットなどのニュースで知り、「ロシアがウクライナに対して戦争をしかけた」と認識したことだろう。廣瀬さんは、同記事で「全く大義のない戦争が始まった」と端的に表現した。
ロシアのプーチン大統領が国営テレビを通じて行った緊急演説(NHK訳)によると、その目的は、「ウクライナ政府によって虐げられ、ジェノサイドにさらされてきた人々を保護すること」や「ウクライナの非ナチ化と、非軍事化」だという。「流血のすべての責任は、全面的に、完全に、ウクライナの領土を統治する政権の良心にかかっている」とした上で、「ロシアは世界で最も強力な核保有国の一つ」であり、「我が国への直接攻撃は、どんな潜在的な侵略者に対しても、壊滅と悲惨な結果をもたらすであろう」と警告した。
つまり、プーチン大統領は、単に隣国への攻撃を指示するだけでなく、世界に対して「核の脅し」を明示的に語ったのである。よく語られる「核抑止論」(核兵器は強力すぎ、使用すると破滅的な被害をもたらすので、核保有国が相互に使うことをためらい、むしろ戦争を抑止するという考え)が成り立たず、むしろ、核保有国であるがゆえの「脅し」をきかせながら、隣国へ侵攻する姿勢は世界を震撼させた。
普段から国際関係に鋭敏なアンテナを張っている人でもない限り、なぜ、この時期に、こういったことが起きたのか、唐突感をいなめず、困惑することになっただろう。
一方、ロシアとその周辺の旧ソ連国家の関係を専門とする廣瀬さんにとっては、さらに大きな衝撃だったという。「目覚めると世界が変わっていた」とまで語ったそのあとには、このように書き連ねた。
「その日、私は重要な研究対象の一つを失い、これまでの研究人生で構築してきたセオリーは水泡と化した」
「前夜まで、私は「侵攻はない」と自信を持って主張していたのだ。しかし、侵攻は起きてしまった。その時、「私が知っている」ロシアは消滅し、私が構築してきた議論も崩壊した。自分の長年の研究は何だったのだろうか、そして人間は戦争を防げないのか、という絶望的な気持ちに苛まれた」
廣瀬さんは、「旧ソ連」の研究者である。「ロシア」というよりは、1991年にソビエト社会主義共和国連邦が崩壊した後でできた、ロシアやウクライナを含む「旧ソ連」諸国をテーマにして、特に「未承認国家」と呼ばれる政治的構成体をめぐる現象からロシアの周辺国政策を考える独自の切り口を提案してきた。
未承認国家とは、主権宣言を自ら行い、国家の体裁を整えながらも、国際的な承認を得ていない「国」のことを指す。現在、地球上のすべての陸地は(南極大陸などごく一部の例外を除いて)、どこかの国に属するので、未承認国家はいずれも、国際的な承認を得た国の領土の中の一部を実効支配する形で打ち立てられる。
実は、ロシアのウクライナ侵攻の3日前に、旧ソ連の未承認国家をめぐる大きなニュースが世界を駆け巡った。ウクライナ東部にある、自称「ドネツク人民共和国」と自称「ルガンスク人民共和国」を、ロシアがともに国家承認したのである。現状では、ロシアに続き、シリアと北朝鮮が両「人民共和国」を承認しているものの、もちろん、他の大多数の国々が国家と認めない以上、これらは未承認国家のままではある。しかし、ロシアは独立した主権国家として扱うことにしたため、24日の侵攻も、こと東部での動きについては、「ネオナチによるロシア系住民の虐殺」を訴える2つの人民共和国から「友好および協力に基づく条約」に基づき要請されたものと主張することができた。
それを言うならば、2014年にロシアがウクライナのクリミア半島を併合した過程の中でも、一度は、クリミア半島の親ロシア勢力が独立を宣言し(この時点では未承認国家)、ロシアが独立国として承認した上で(この時点でも、ロシア以外の国からは未承認国家には違いない)、国民投票を実施、その結果を受けて、ロシアに併合するという手続きを取った。独立宣言から国民投票まで5日間、さらにその翌日には併合という早業だった。
未承認国家という国家ならざる何かが、梃子(てこ)のように使われ、一連の大きな出来事に至っている感がある。
廣瀬さんは、旧ソ連の紛争や未承認国家研究を軸にロシアの外交政策を論じ、近年はロシアがさかんに活用しているとされる、サイバー戦争、情報戦、民間軍事会社による非正規戦など、様々な手法を混合させた「ハイブリッド戦争」の研究も深めてきた。本稿では、そのような他にはない視点を持った廣瀬さんから、現在進行中の「戦争」がどのように捉えうるのかを見ていく。それによって、「ウクライナ侵攻」をめぐる背景の理解を、より広く分厚くできるのではないかと目論んでいる。
さらに言えば、「目覚めると世界が変わっていた」「自分の長年の研究は何だったのだろう」と率直に語る専門家であるからこそ、話を伺いたいと思ったことも動機のうちの大きな部分だと申し添えておく。「侵攻」の開始から、およそ半年がたち、局面が膠着状態になっている感がある今、「何が違っていたのか」「そこから何を導くことができるのか」まで話を進められればよい。
©National Geographic Society