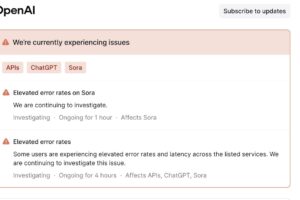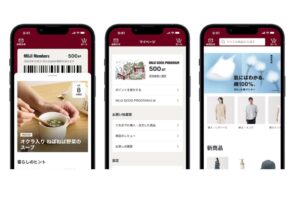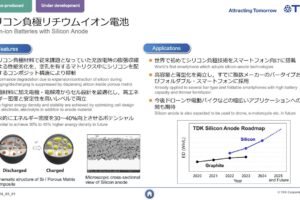東京, 7月29日, /AJMEDIA/
近年では、メタバースを学校に活用する取り組みも増えてきたように思える。全国の国公私立小中学校で2021年度に30日以上欠席した不登校の児童生徒は24万を超え、過去最多となったようだ。それに伴いオンラインでの授業やオンデマンド授業の導入も増え、学校での授業の形も多様化してきた。
例えば埼玉県戸田市では、メタバースで不登校児を支援することを目的に、「メタバース登校」という取り組みも行っている。そのほかにも、高卒資格も目指せるメタバースの学校「MEキャンパス」という取り組みもあるようだ。
筆者の齊藤は、友人のタロタナカさんと「私立VRC学園」という学校コミュニティを2020年にVRChat上に創設し、参加したユーザーたちと共に運営を行ってきた。私立VRC学園は公式の学校ではなく、我々がVRやメタバースを日頃嗜んでいるなかで、「VR空間に学校を作ったら面白いのでは?」というところから始まった活動である。
【過去記事:なぜメタバースに学校を作ったのか–VRChatのコミュニティ「私立VRC学園」を振り返る】
そこで今回は、筆者自身が実際にメタバースに学校コミュニティを作ってみた経験から感じたメタバースの学校ならではの学校の在り方、そしてそこから得られたこれからの教育への新たな示唆について取り上げる。
筆者らが取り組んだ私立VRC学園は、「多種多様のバックグラウンドをもった人たちが集まり、交流し、生み出す、インフラ的存在の空間をVR上に作る」という目的のもとスタートした。私立VRC学園では、メタバース空間に建築された校舎で、教室では通常の学校のように授業が行われる。1コマ30分から1時間ほどの授業で、開催期間中(一学期二週間程度)の平日は毎晩授業が行われる。
授業内容もユニークかつメタバースならではのものが多く、これまでにも、
VRダンス講座
VRで使える英会話
VRで使えるコミュニケーション講座
VRChatのイベントに関する講座
ボイスチェンジャー講座
VR DJ講座
などを開催してきた。
先生と生徒も、定期的に新学期を開き、そのたびに募集をしている。VRChat初心者が基本的には対象だが、長くVRChatをプレイしている人たちも、参加可能である。
【過去記事:世界で最も“カオス”なVR空間「VRChat」とはなにか–その魅力から始め方までを解説】
趣味でメタバースに学校コミュニティを作ってみて、筆者が気がついたメタバースを教育に活用するためのポイントは、「多種多様のバックグラウンドをもった人たちが集まり、交流し、生み出す」という点だ。
メタバースブームに便乗し、あらゆるものをメタバースで置き換えるような取り組みが見られるが、ただ単にリアルをバーチャルに置き換えるだけでは、メタバースの良さを活かしきれない。例えば、メタバースの活用を既存の学校の内側のみで行なってしまうと、コミュニティの範囲が既存の学校からはみ出ることがなくなってしまう。そのため、その学校に馴染めない学生にとっては、リアルだろうがメタバースだろうが、あまり関係がない。
不登校の学生によくあることとして、話す機会がないということだ。親やスクールカウンセラーくらいしか話す相手がいない、あるいはインターネットに頼るしかない。学校には行きたくないけど誰かと話したい。メタバースでは、相手の素性を知る必要もなければ、自分の素性を明かす必要もない「居場所」の実現ができる。しかし、メタバースの活用が学校の内側のみであれば、その特性を活かすことができない。
私立VRC学園の例のように、メタバースの学校が「外にひらけた空間・コミュニティ」であれば、多種多様のバックグラウンドをもった人たちが集まる。そして、そこに集まった人たちは基本的にアバターを使って参加するため、見た目や年齢、性別、国籍、ハンデキャップなど、物理的制限をある程度無視することが可能である。また、アバターは身長なども変えられるので、子供も大人相手に積極的に会話を進めることがしやすくなる。
例えば、大人が子どもに対して、大人のように振る舞うことを期待していると、子どもは期待に沿うべく育つ。反対に、大人が子どもを赤ちゃん扱いすると、相手もその期待を満たす行動を取るようになる。これは「ピグマリオン効果」と呼ばれるが、メタバースでアバターを介したコミュニケーションは、その効能を生みやすいと感じている。