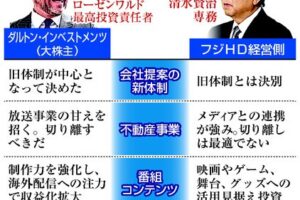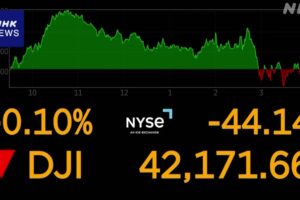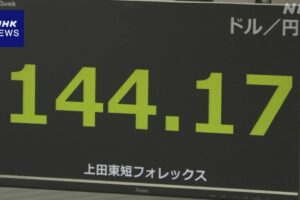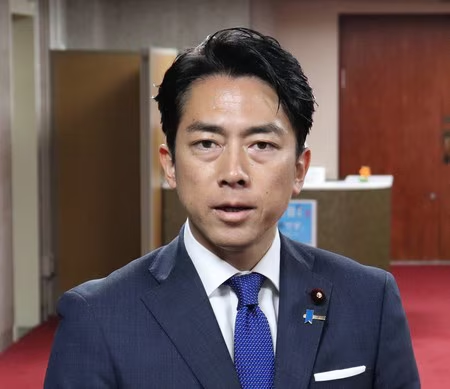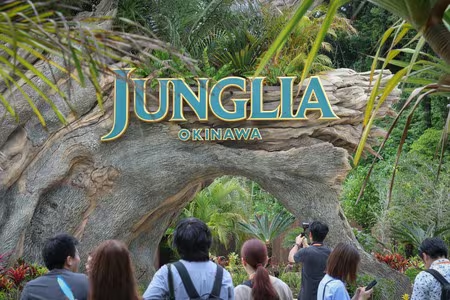東京, 1月23日, /AJMEDIA/
感覚的なことだが、最近、道路が車で混んでいる気がする。新型コロナウイルス禍で停滞していた経済活動が復活してきたからなのか。電車より車の方が感染対策上、安全だと思っているのか。ところが、ガソリン価格が上昇し、車を活用している人を困らせている。産油国の石油減産、コロナ禍からの経済復活、物流の停滞などが理由だと考えられる。いずれにしても、2050年にカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量の実質ゼロ)宣言したにもかかわらず、二酸化炭素(CO2)を排出するガソリン頼みである。矛盾していると思わざるを得ない。今や、各国政府ならびに企業がCO2排出対策を競っている。それは地球温暖化を防がねばならないからだ。(文 作家・江上 剛)
◆守るべきは地球でなく人間
温暖化が後戻りできない気温1.5度上昇のティッピングポイント(臨界点)に達するのは30年、いやもっと早く28年ともいわれる。ポイントに達すると、サンゴなどが死滅し温暖化が加速するとされる。
「18年現在の大気二酸化炭素濃度は400ppmだ。過去80万年間の気候データでは、このレベルに到達した時期はまったく見当たらない。(中略)二酸化炭素濃度は、18世紀の産業革命以降に急速に上昇しており、その原因が人類にあるのは化学指標の結果からも示されていて、議論の余地はない」(「地球46億年気候大変動」横山祐典著、講談社ブルーバックス)。
地球温暖化は人類が原因なのである。青い地球を守れ、と言うが、それは地球を守ることではない。人類の生存を守ることなのだ。
地球温暖化を放置すれば、地球は暑くなり、氷は溶け、海面は上昇し、多くの生物が死滅し、広大な農地が砂漠化し、農産物が収穫できなくなり、人類は生きることができなくなる。
「私たちが行動を起こすのは、”地球を救う”ためでは決してない。45億年以上、激しい変化の中を生き続けてきた地球を、私たちが救う必要などない。(中略)それは何よりも人間という種のためであるべきだ。誰よりも危機に瀕(ひん)しているのは私たちなのだから」(「地球進化46億年の物語」ロバート・ヘイゼン著、円城寺守監訳、渡会圭子訳、講談社ブルーバックス)。
たとえ温暖化しようと、地球は生き残る。しかし、人類や現在の動植物は死滅するだろう。
しかし、ヘイゼンは「他の脊椎動物(鳥かもしれない)が取って代わる。最近、とくに速く進化するということがわかったペンギンが、姿を変えて広がり、隙間を埋めるかもしれない」と、クジラのようなペンギンや虎のようなペンギンが現れるかもしれないと書く。「猿の惑星」ではなく「ペンギンの惑星」になるかもしれないのだ。
最近、富裕層の中には宇宙旅行に熱を上げる人がいるが、SFの世界ではなく、地球外への移住を先取りする動きなのかもしれない。
◆国家間のビジネス競争
さて、地球温暖化を防がねば、人類の危機であることは間違いないとしても、最近の世界の動きはCO2削減が国家間のビジネス競争になっている気がしないでもない。
欧米と中国とで国際標準づくりを競い合い、EV(電気自動車)化をいつまでに達成するかで戦っている。ガソリンエンジンの技術、ハイブリッド技術で世界を席巻した日本は、片隅に追いやられてしまう可能性がある。
そこで、日本政府も20年10月に50年カーボンニュートラルを表明し、30年度のCO2を46%削減、さらに50%削減を目指すことにした。それに呼応して多くの企業が「脱炭素宣言」を発している。
これは本当にいいことである。このまま地球温暖化が進み、人類が滅亡するのであれば、世界第3位の経済大国である日本にも大いに責任があるからである。
カーボンニュートラル実現に向けた政府のエネルギー基本計画(21年10月)を見てみる。わが国のエネルギー政策はS+3Eが基本である。Sはセーフティー(安全)、Eはエネルギーセキュリティー(安定供給)、エンバイロメント(環境)、エコノミックエフィシェンシー(経済性)が基本である。
カーボンニュートラル対応のポイントとしては「安全の確保を大前提に、安定的で安価なエネルギーの供給確保は重要。この前提に立ち、50年カーボンニュートラルを実現するために、再エネについては主力電源として最優先の原則の下で最大限の導入に取り組み、水素・CCUS(CO2の回収、貯留)については、社会実装を進めるとともに、原子力については、国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していく」と書かれている。
安全性が大前提になっているのは東京電力福島第1原発の事故が、いまだに収束していないからだ。
◆化石燃料は輸入頼み
このポイントを読んでも、なるほどとはうなずけず、懸念ばかりが湧き起こるのは、日本が現在の経済力、生活水準を維持し、さらに向上させるためには、どれだけのエネルギーが必要なのかが分からないからだ。
他国では化石燃料による発電を、太陽光や風力などの再生可能エネルギーに依存した結果、大規模な停電が起きているとの情報もある。
私たちの周囲を見渡すと、先に触れたように自動車がなくては暮らせない。野菜や果物などの農産物のみならず、畜産と漁業も化石燃料頼みである。冬の寒さをしのぎ、夏の暑さに耐えられるのも化石燃料から生み出される電気があればこそである。
日本は電気を生み、暮らしを豊かにする石油など、化石燃料の多くを海外に依存している。エネルギー自給率はたったの11.8%(18年)で、先進各国の中で最も低い国の一つである。こんな国が、本当にカーボンニュートラルを実現できるのだろうか。
エネルギー基本計画に美辞麗句を並べるだけでなく、政府は不都合な真実を直視し、国民にエネルギーの現状を説明し、脱CO2がいかに困難な課題であるか、真摯(しんし)に訴えかける必要があるだろう。
エネルギーに関する日本の不都合な真実とは何か。18年度の日本のエネルギー構成は石炭25.1%、石油37.6%、LNG(液化天然ガス)22.9%。化石燃料が85.5%にもなる。そして、それらのほぼ全量を海外からの輸入に頼っていることだ。
これらの安定供給は、供給先の国に頼らざるを得ない。原油の供給先は中東地域に約88%を依存する。これらの国々に紛争が起き、供給が削減されれば、かつてのようなオイルショックが再来する。また、他国が資源を高値で買い占めることがあっても同じような危機に陥る。
日本が太平洋戦争に突入したのは、米国が日本に対して石油を禁輸したことも一因であるといわれている。戦争を起こしてまでもエネルギーを確保しなければならなかったのだ。この事実は重い。
日本の経済や生活を支える第1次エネルギーが決定的に不足しているという事実を冷静に見詰める必要がある。その上でのカーボンニュートラルなのだ。
◆原発が絶対に必要なら
日本は、石油備蓄などに努力しつつも、新しいエネルギーとして原子力発電に注目した。その結果、各地に原発がつくられた。ところが、福島第1原発の事故で、原発の安全性に大きな疑問符が付いた。
このため、現在54基ある原発のうち、稼働しているのは5カ所、9基のみである。原子力によるエネルギー供給は2.8%(18年度)にすぎない。
政府は基本計画の中で、30年度には原子力で20%から22%を賄うとしている。しかし、既存原発には設置後30年から40年経過しているものも多い。
原子炉等規制法によると、原発の運転期間は40年(特別な場合はあと20年延長)となっており、多くの原発が稼働停止に追い込まれる。
政府は基本計画で、原発の再稼働を進めると明記しているが、使用済み核燃料問題や最終処分地の問題などに、どれだけ喫緊の問題として取り組んでいるのか、私たちにはあまり見えてこない。
再稼働すると明記した以上、立地自治体だけを説得すればいいというわけではない。国民全体の問題である。カーボンニュートラルを実現するために原発が絶対に必要なら、不都合な真実から目を背けず、国民の理解を得ることを急ぐべきではないか。
◆太陽光パネルの問題点
基本計画で再エネは30年度に36~38%にするとした。内訳は太陽光14~16%、風力5%、地熱1%、水力11%、バイオマス5%である。再エネの不都合な真実とは、太陽光パネルの製造は、ほとんど中国メーカーであるということだ。
世界の太陽光パネルの58%が中国製である。トップ10のうち、中国が7社ランクインしている。これでいいのだろうか。
コロナ禍でマスクが消失し、経済安全保障ということがいわれている。中国に多くの物資の製造を依存していることは、日本にとって非常に危険である。冬季北京五輪において米国に同調し、外交的ボイコットを選択したり、台湾有事が発生したりすれば、たちまち太陽光パネルが消失するだろう。
こんな不安定なものに期待が大き過ぎないか。日本のメーカーを育てることは基本計画にはなく、中国製パネルを駆逐できるほどの太陽光発電の画期的な新技術開発などに国策として取り組まねばならないのではないか。
さらに、太陽光パネルの廃棄問題である。太陽光設備の法定耐用年数は17年である。それ以上使用可能かどうかは分からないが、いずれにしても破棄の問題がある。これは原発の使用済み核燃料と同じように、いずれ大きな問題になる。
耕作放棄地に設置されていることが多いが、発電事業後の農地への原状回復が可能か。法的に義務付けられているが、法令順守されるか監視が必要だ。
事業が終わっても撤去されないパネルがあちこちに散乱することになったら、大問題である。また、太陽光パネルには鉛、カドミウムなどの有害物質が含まれており、これらを適切に処分しなければならない。
いずれの時期にか、太陽光パネルの大量破棄が到来する。その際は、産業廃棄物の6%にも及ぶとの試算もある。
19年の日本の産業廃棄物は約3億8000万トンであり、その6%は約2280万トンである。パネル設置ばかりに目を奪われず、破棄問題にも今から対策を講じておく必要があるだろう。
◆再エネも外国依存でいいのか
風力発電も同じである。巨大な風車メーカーは中国を含む外国メーカーばかりであり、風力発電の有力企業には中国企業がずらりと並ぶ。日本メーカーの名はない。これも経済安全保障の観点から問題である。
再エネも化石燃料と同じようにほぼ全てを外国(それも今度は中国である)に依存していいのだろうか。
「景観を害する」「設置の適地が少ない」等の問題もある。静岡県熱海市では太陽光パネルを設置した場所が土石流で崩れ、大きな被害が出た。山肌を削り太陽光パネルが設置してある光景は、日本のような山国には危険極まりないものに見えた。
風力発電でも山の稜線に設置してある地方があり、そこでは山崩れの危険があるとして設備の撤去を求める問題が起きている。これから多くの地域で同じ問題が起きる可能性がある。
基本計画には「地域と共生する形での適地確保」と書かれているが、適地はあるのだろうか。国立公園内に風車が林立する姿を見たいと思う国民は少ないのではないか。
注目を集める水素については基本計画に「水素を新たな資源として位置付け」とあるが、水素は石油や石炭のようなエネルギー資源ではない。
このことも不都合な真実として国民に説明する必要がある。水素は単体で存在していない。水を分解して得るものである。分解には大量のエネルギーが必要となる。
CO2削減のために分解に使用するエネルギーを太陽光パネルで発電し、燃料電池として使用するまでに、最初のエネルギーは約3分の1程度まで低減するという意見もある。非常に非効率なエネルギーであり、社会的コストが高くなる。決して夢のエネルギーではないのである。
◆目を背けてはいけない
いずれにしてもカーボンニュートラルの実現は容易ではない。そのことを政府は直視し、国民に正直に説明することが求められる。その上で、国民運動としてこの実現に向けて努力するべきだろう。
私たちは、エネルギーがなければ経済を発展させることもできなければ、現在の生活の維持もできない。
日本には何が最適なのか。各家庭、各地域でマイクロ水力発電を行うことがいいのか。日本の自然環境にふさわしい水力をもう一度、見直すのがいいのか。
少なくともカーボンニュートラル実現に向けて、不都合な真実から目を背けないようにするべきだ。そうでないと、将来に禍根を残すことになるだろう。
(時事通信社「金融財政ビジネス」より)
【筆者紹介】
江上 剛(えがみ・ごう) 早大政経学部卒、1977年旧第一勧業銀行(現みずほ銀行)に入行。総会屋事件の際、広報部次長として混乱収拾に尽力。その後「非情銀行」で作家デビュー。近作に「創世(はじまり)の日」(朝日新聞出版)など。兵庫県出身。