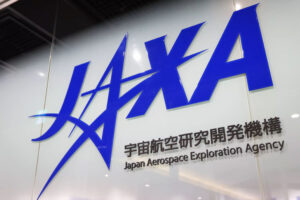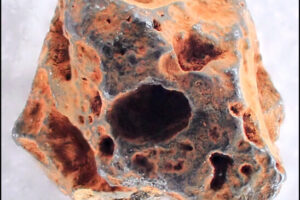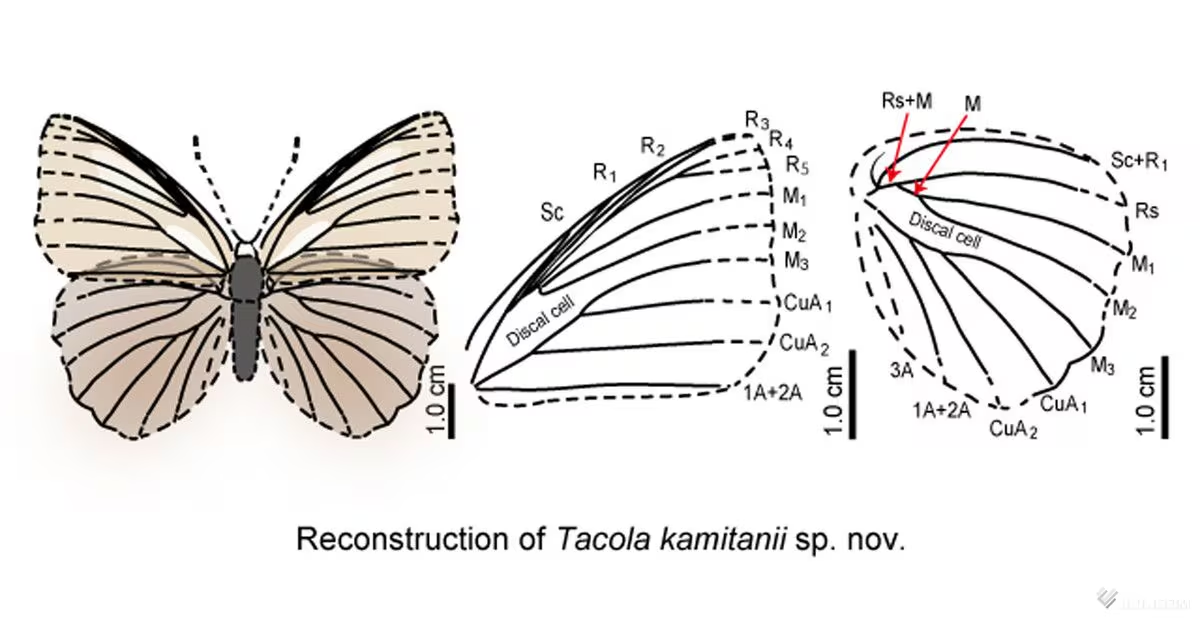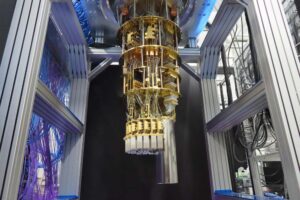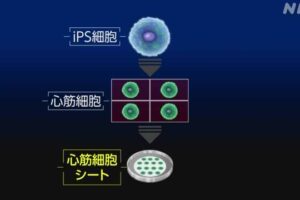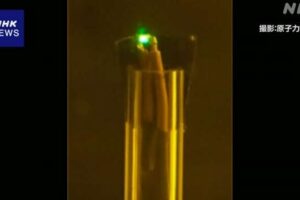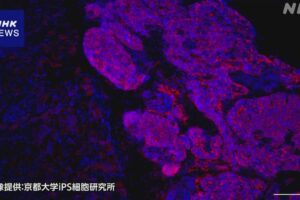東京, 3月20日, /AJMEDIA/
日本語教師としてウクライナで教えた経験から、現地の大学や大使館との橋渡し役となって、同国の学生を東京都の東洋大へ留学生として受け入れることに奔走した。戦火が続く中、学びのともしびを絶やさないようにと学生を支援している。
神戸市出身で筑波大を卒業後、自動車メーカーの研究職に就いた。会社では初の女性総合職として仕事に打ち込んだが、「もっと人を相手に働きたい」という思いは募った。
転機は一九九五年の阪神大震災だった。変わり果てた故郷を見て「何があるかわからない。好きなことをやろう」と決めた。資格を取得し、日本語教師になった。米国で教えた後、日本政府が教師を海外派遣するプログラムに応募した。派遣先は選べない。ウズベキスタンで一年間教え、続いて一九九九年から二年間、教えたのがキーウ(キエフ)国立大だった。
当時はソ連崩壊後の混乱期で貧困が色濃かった。ただ、街並みは美しく「人々は文化的だった。バイオリンを手放さず、シェフチェンコの詩を暗唱していた」と振り返る。学生は休日も教えを請うてくるほどで、期待に応えようと熱心に指導した。
アゼルバイジャンやロシアでも教え、帰国後は大学教員の道へ。東洋大には二〇一七年に着任した。
そして昨年二月、ロシアの侵攻が始まった。ニュースに映し出される惨状に、矢口悦子学長と留学生受け入れの話を進めた。キーウの国立大や市立大で教員をしているかつての教え子らに打診すると「ぜひ送り出したい」と喜んだ。大学間協定を結ぶ際は、在日ウクライナ大使館で書記官をしている教え子を通じ、駐日大使にも掛け合った。
五月から留学生が来日した。週一日は全員が集まる授業を設け、日本の学生有志には日本語サポーターとして参加してもらった。
当初、留学生たちが泣いている姿も目にしたが、やがては日本人学生と他愛のないガールズトークをするようになった。「安心しました。穏やかな環境で学んでもらえた」。日本人学生も異文化交流を肌で感じた。「最初は戸惑いもあったと思うが、頑張ってくれた」
留学生の多くはこの春に帰国する。「生きていてほしい。それだけで良い」と願う。彼女らが活躍する日が来るはずだ。「今、種をまいておく必要がある。何十年か先の未来のために」(浜崎陽介)