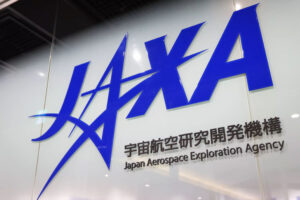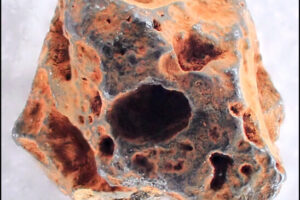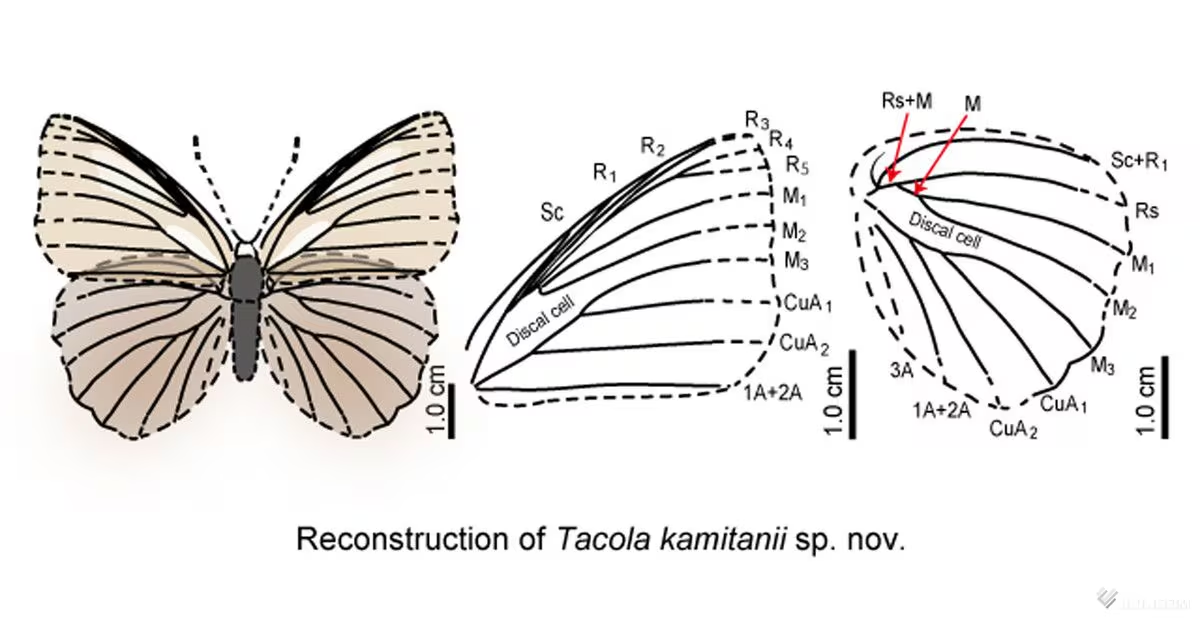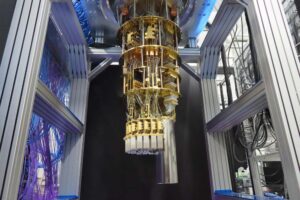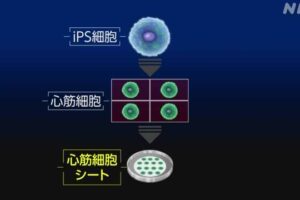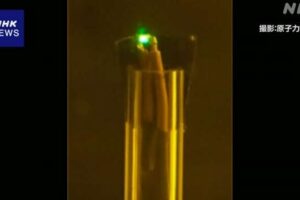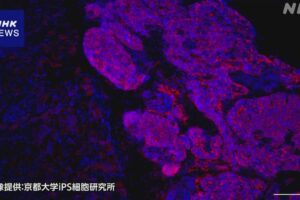東京, 7月25日, /AJMEDIA/
感染が急速に拡大している新型コロナ以外にも、子どもを中心に注意が必要な感染症の一つが、およそ4年から6年の周期で流行を繰り返しているおたふくかぜです。
現在、任意接種となっているおたふくかぜのワクチンについて、小児科医で作る学会などは定期接種化に向けた大規模調査を行っていますが、新型コロナなどの影響で調査があまり進んでおらず協力を呼びかけています。
おたふくかぜワクチン接種 対象者の4割程度
「流行性耳下腺炎」、いわゆる、おたふくかぜは子どもを中心に流行し、発熱や耳の下の腫れを引き起こすウイルス性の感染症で1000人に1人ほどの割合で難聴になるという報告もあります。
しかし、重症化を防ぐためのワクチンは現在、任意の接種となっていて、対象者の4割程度しか受けていないということです。
定期接種化に向け全国調査も…
このため日本小児科学会などは、公費で接種が受けられるよう、定期接種化に向けた議論の参考にするため全国調査を進めています。
国から今年度末までに10万人から20万人規模のデータを集めて、無菌性髄膜炎などの副反応の発生割合やその因果関係を調べるよう求められていますが、新型コロナやワクチンの供給不足の影響で、現在集まっているデータはおよそ3万5000人にとどまっているということです。
このため学会などでは、1歳から小学校就学前の子どもの保護者と接種を行う医師に対して、調査への参加を呼びかけています。
研究グループの代表を務める神奈川県衛生研究所の多屋馨子所長は「おたふくかぜの流行はいつ始まってもおかしくない。大きな流行が来る前に、定期接種化に向けた議論のそ上にのせるためぜひ協力をお願いしたい」と話しています。
おたふくかぜ “1000人に1人ほどの割合で難聴” 報告
おたふくかぜにかかり難聴になった人は、日本耳鼻咽喉科学会の調査で2015年からの2年間だけで全国に少なくとも359人にのぼったことがわかっています。
また、学会によりますと、1000人に1人ほどの割合で難聴になるという報告もあります。
耳元の大きな声でも聞き取りにくいなど重度のケースが多く、大半は治療しても回復が難しいということです。
佐賀県に住む高校2年生の山口友花さん(16)は、小学3年生のときにおたふくかぜにかかり左耳が難聴になりました。
呼びかけられたときにどこから声が聞こえたのか分からなかったり、人混みで会話が聞き取れなかったりして、コミュニケーションをとるのが困難になりました。また、平衡感覚がくずれ、めまいの症状にも悩まされたということです。
いまは「人工内耳」という装置をつけて声や音を認識していますが、以前の聴力は戻らず、聞き取りづらい音があったり騒がしい場所は苦手だったりします。
友花さんは「相手の話が聞き取れなくて何回も聞いてしまい、『もう大丈夫だよ』って言われたこともありました。片耳が聞こえなくなりすごくつらかったので、自分と同じようにおたふくかぜで難聴になる子が1人でも減ってほしい」と話しています。
母親の眞丘さんは「おたふくかぜはみんなかかるもので、まさか難聴になるとは思わずワクチンを打っておけばよかったです。多くの人にワクチンを打ってほしいし、定期接種化を早く実現してほしい」と話しています。
小児科の医師など “公費によるワクチン定期接種化を”
重症化を防ぐためのおたふくかぜのワクチンですが、副反応の「無菌性髄膜炎」が相次いで報告されたため、1993年に公費で受けられる定期接種ではなくなり、現在は自己負担による任意接種となっています。
接種費用の助成を行っている自治体もありますが、接種しているのは対象者の4割程度だということです。
ワクチン接種後に無菌性髄膜炎を発症するのは1600人から2300人に1人とされていますが、データによって差があるほか、小児科の医師などからは、おたふくかぜにかかって難聴になるリスクを考えると、誰でも公費で受けられる定期接種化を求める声があがっているということです。
研究グループの代表を務める神奈川県衛生研究所の多屋馨子所長は「無菌性髄膜炎は命に関わるような重い病気ではないが、ワクチンの副反応で起こってしまうことがある。おたふくかぜにかかると難聴になってしまうことがあるということも理解していただいたうえで、予防のためにワクチンを接種してほしい」としています。