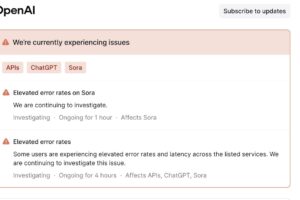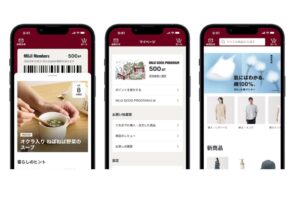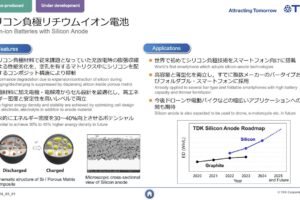東京, 6月4日 /AJMEDIA/
スプレッドシートを編集するときは、手に持った小さなオレンジ色の四角いデバイスに向かって、グレーのボタンを押しながらこう話すだけでよかった。「このスプレッドシートを書き写して、列Bと列Cを入れ替えて」。そうすると、ほぼ一瞬で、メールの受信箱に変更されたスプレッドシートが届く。驚くほど見事な機能だ……そう感じたのは最初だけで、すぐに、1列目の語句が切り詰められていることに気づいた。
「rabbit r1」を使ってみた筆者の体験は、大体そんな感じだった。rabbit r1は、アプリを搭載せず人工知能(AI)を使ってタスクを処理する、199ドル(約3万1000円)のハンドヘルドデバイスである。いろいろな機能がうまく動き、創設者のJesse Lyu氏がこのデバイスを「Pokedex」(1990年代に米国で発売された玩具)の「現実世界」版と呼ぶ売り文句に納得できる瞬間もあった。
だが、期待どおりに機能しなかったときの方が、はるかに多い。「Uber」や「Doordash」など、現在rabbit r1で使えるサービスにしても、スマートフォン上で操作するよりずっと制限があるように感じる。それも、とりあえず機能したとしてだ。ニューヨーク市の街を観光したときは、一部のランドマークを識別できないこともあったし、インターネット接続が切れることもあった。バッテリーの持続時間もひどく短かった(編集部注:その後のアップデートで改善されている)。
rabbit r1は小型のハンドヘルドガジェットで、操作は主に音声コマンドで行う。ユーザーがアプリを使うのではなく、OSの土台として動くソフトウェアが、AIを使ってユーザーの代わりにデジタルアプリおよびサービスの操作方法を学習する、とLyu氏は説明している。斬新なコンセプトだが、やがてはこの形態が普及して、将来的には何か操作するとき主流の形になる、というのがLyu氏の考えだ。
そう考えているのは、Lyu氏だけではない。rabbit r1を事前予約したファンたちは、米国時間4月23日にニューヨークで開催された発表イベントに、一番乗りで実機に触れようと列を成した。筆者が列に並びながら話を聞いた男性などは、わざわざマサチューセッツ州から車で駆けつけたということだった。
しかし、現行バージョンのrabbit r1は、そうした崇高な目標に手が届いていない。Uberで車を呼べるし(少なくとも、そのはずだ)、Doordashで料理を注文できる。「Midjourney」で画像を生成することも、「Spotify」で楽曲を再生することもできる。質問に答える、発話を翻訳する、カメラを使ってビジュアル検索エンジンになるなど、いろいろな機能がある。斬新で興味深いものの、その操作の多くは、現在のスマートフォンと比べるとやはり劣って感じる。全体的に、rabbit r1はまだ道なかばであり、これまでにうたわれてきたAI革命というよりは、将来性に対する賭けといった印象を受ける。
レトロなデザイン
rabbit r1で成功している点が1つあるとすれば、それはデザインだ。サイズは一般的なスマートフォンの半分ほどで、本体は楽しげな明るいオレンジ色。2.88インチの小型ディスプレイを備え、ナビゲーション用のスクロールホイールと、800万画素のカメラを搭載する。SIMカードスロットもあり、セルラー通信にも対応するが、筆者はWi-Fiネットワークと自分のスマートフォンのモバイルホットスポットに接続して使った。