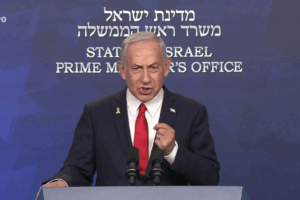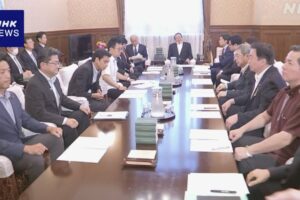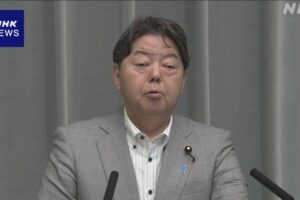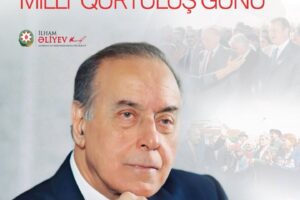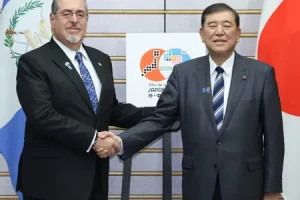東京, 9月1日, /AJMEDIA/
未承認国家に着目して、2022年時点のロシアによるウクライナ侵攻まで見通すための起点として、まず廣瀬さんが拠点にしたアゼルバイジャン共和国が抱える未承認国家「ナゴルノ・カラバフ共和国」がとのように成立したか見た。今回は、引き続いてその経緯を確認した上で、さらに先に進む。
かつて、日本に入ってくるナゴルノ・カラバフ紛争にまつわる情報は、ほとんど欧米経由で、その場合、ほぼアルメニア側の主張が採用されていたと前回書いた。
その理由はというと、アルメニア側が、アゼルバイジャン側に対して、はるかに情報発信に長けていたからだという。その鍵となっているのが「アルメニア人ディアスポラ」だ。
「ディアスポラというのは、世界中に離散したユダヤ人のことをもともと指しますが、ユダヤ人以外でも、自国の外で暮らす人たちをそう呼ぶことがあります。アルメニア人ディアスポラもそうで、本国にいるアルメニア人が300万人ほどなのに対して、その倍以上が世界各国に散っているんです。彼らは多言語で発信するのに長けています。英語やフランス語でばんばん発信します。今は、英語が堪能なアゼルバイジャン人も増え、またSNSなどで情報発信も容易になりましたから、アゼルバイジャンからの情報も増えていますが、かつて、日本で見られたナゴルノ・カラバフ関連の情報は大体英語の翻訳だったんですよ。だから、アルメニア人がかわいそうで、アゼルバイジャン人はひどいという内容になっていきます。一方、当時のアゼルバイジャン人は、アゼルバイジャン語と、せいぜいロシア語でしか発信できなかったのですよね。わたしがアゼルバイジャンに留学したのも、現地の言葉を学んで、直接、生の情報に触れたいと思ったこともあるんです」
そのような強力なディアスポラの存在は、ガス田や油田のような天然資源のないアルメニアにとって、大きな力となっている。アルメニアもナゴルノ・カラバフも、国外にいる同胞からの直接間接の支援にかなり助けられてきた。それは金銭的なことに留まらず、アルメニア人ディアスポラが、それぞれの居住国の政府に対して行うロビー活動を通じて得る利得も含まれている。
「アルメニア人ディアスポラは世界中にいて、商才に長けていて、大金持ちも多く、特にアメリカだとかなりの票田を持っているわけです。そこで、アメリカの政治家はとても気を遣っていて、その力の大きさといったら、アルメニア・ロビーに対抗する形でイスラエル・ロビーとオイル・ロビーが組んでかかっても勝てないほどと言われています。ひとつ具体的に言いますと、アメリカ議会は、アルメニア・ロビーの圧力で、『アゼルバイジャンに対して人道支援以外の経済支援を一切行わない』という制裁法(自由支援法 S.907)を1992年に通しました。その後、その時々の大統領がこの法律を撤廃しようとしたんですが、アルメニア・ロビーの抵抗で果たせませんでした。2001年の同時多発テロ以降は、対テロ戦のためにイランと国境を接したアゼルバイジャンの協力が不可欠なため、この法律を、1年間の『時限的無効』を毎年延長することで事実上無効化し、同時にアルメニアの顔を立てるという方法に落ち着きました」
他にも、カナダ、フランスなどで、アルメニア人ディアスポラのロビー活動がきわめて強力だという。そして、このような国外の同胞がいるがゆえに、アルメニア人の未承認国家である「ナゴルノ・カラバフ共和国」の支援国として、アルメニア本国とロシアだけでなく、アメリカやフランスも挙げられることになるのである。
もっとも、ロシアにとっては、前回見たとおり、未承認国家は勢力圏の維持のためのツールであり、「ナゴルノ・カラバフ共和国」も全時期というわけではないが、その例にもれないと言える。
まず、ソ連解体後の第二期目の政権が、大きく親欧米・反ロとなっていた(つまり、ロシアとしては勢力圏に留めたい)アゼルバイジャンに対しては、ロシアは、1994年に停戦へと導いた見返りとして、旧ソ連諸国で作る独立国家共同体(CIS)やCIS集団安全条約機構に加盟させ(後者は、後に脱退)、アゼルバイジャンの石油をめぐる国際交渉を仕切り直させることもできた(ただし、アゼルバイジャンは2000年代半ば以降、オイルマネーで経済成長し、欧米・ロシアの間で絶妙なバランス外交を展開するようになった)。
また、紛争のもう一方の当事者国であるアルメニアに対しても、「ロシアが支援したからこそナゴルノ・カラバフ紛争に勝てた」という事実をもって、従属的な立場に置くことができた。
これらだけでも利得といえるが、ロシアによる「未承認国家」の利用は、もう一段、深いところにある。紛争の焦点だった「ナゴルノ・カラバフ共和国」に対して直接的な影響力を持つことができれば、「未承認国家」はさらに使い勝手のよいものになるからだ。
「他の旧ソ連の未承認国家と異なって、『ナゴルノ・カラバフ共和国』を支えるものとして、アルメニア本国に加えてアルメニア人ディアスポラの存在が大きかったので、ロシアは長年、この『国』に直接的な影響力を及ぼせなかったんです。それが変わったのが、2020年の第二次ナゴルノ・カラバフ戦争です。アゼルバイジャンが全ての緩衝地帯と、ナゴルノ・カラバフ地域の約4割を奪還しました。そして、『共和国』に残った残りの約6割程度の領域の平和維持をロシア軍が担当するようになりました。これによって、『ナゴルノ・カラバフ共和国』に対する影響力も確保できるようになりました。これが意味するのは、本来は外国軍の駐留を認めていない主権国家・アゼルバイジャン領の一部であるナゴルノ・カラバフ地域に、平和維持の名目でロシア軍を駐留させて影響力を行使できる、ということです」
未承認国家に自軍を駐留させるということは、同時に、主権国家の領土の中に自軍を置くことでもある。未承認国家の両面性を使って、影響力を行使したい国の内政に揺さぶりをかけることができる。国際的に正当性を持たない未承認の存在を利用した旧ソ連諸国への影響力確保というのが、廣瀬さんが解明した、ロシアによる未承認国家の利用の骨子だった。
もっとも、「ナゴルノ・カラバフ共和国」を梃子にした、アゼルバイジャンへの揺さぶりについては、必ずしも理論通りにうまくいったわけではないようだ。特に2022年2月以降、この図式が揺らいでいるという。
「2020年の第二次ナゴルノ・カラバフ戦争の停戦後、アゼルバイジャンは、領土をかなり奪還したにもかかわらず、『国内』にロシア軍を置かれていました。理論的には、ロシアは、アゼルバイジャンに揺さぶりをかけられるはずでしたが、それでも、アゼルバイジャンはロシアに従属的な姿勢にはなったとは言えず、さらにロシアのウクライナ侵攻で、ロシア軍の弱さが露呈してからは、アゼルバイジャンおよび多くの国々がロシアを明らかに軽侮するようになったんです。アゼルバイジャンは2022年3月、そして8月に度々ナゴルノ・カラバフに攻撃を仕掛け、紛争を煽っています」
©National Geographic Society