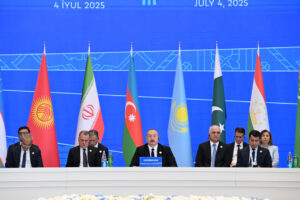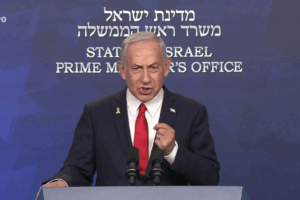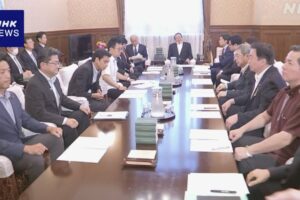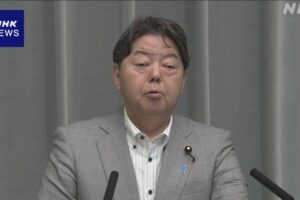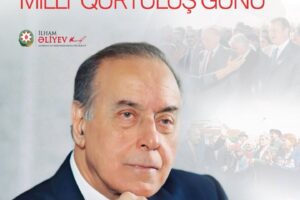東京, 8月26日, /AJMEDIA/
対話型人工知能(AI)「チャットGPT」に代表される「生成AI」の基盤技術に関する各国の開発競争が激化している。初代デジタル相を務めた自民党の平井卓也・党デジタル社会推進本部長は25日までに時事通信のインタビューに応じ、日本は効率的な技術開発など「AI開発の省力化促進」に注力するよう訴えた。主なやりとりは次の通り。
霞が関でAI「利点大きい」 河野太郎デジタル相インタビュー
―これまでの政府の議論をどう見る。
政府は2019年、世界に先駆けて「人間中心のAI社会原則」を打ち出した。ただ、生成AIに関しては、莫大(ばくだい)な物量作戦で進めるイノベーションのため、日本で積極的に進めようとはならなかった。少ない学習データ、少ない電力、少ない計算資源(スーパーコンピューターなど)で結果を出すものでなければ、日本人の感覚に合わないのだろう。
―日本が活躍できる分野は。
効率性や環境負荷を考えた「AIの軽量化」だ。チャットGPTの研究開発は当初、大量の電力を使い、効率性は度外視したプロジェクトだった。しかし、それでは持続可能性はない。国内の民間企業で既に技術開発が進む次世代通信基盤や半導体チップなどの分野は日本がリードできるだろう。
生成AIのビジネスモデルは今、非常に曖昧だ。一定期間の利用で料金を支払う「サブスクリプション型」か、全く異なるモデルか、決まっていない。まだ勝者は誰もいない状態で、日本にもチャンスがある。
―政府の司令塔機能はどうあるべきか。
来年度予算の概算要求では、計算資源の確保や生成AIの研究開発、学習データの整備などを、経済産業省や文部科学省、総務省、内閣府がそれぞれまとめている。ばらばらにならないよう、省庁横断で進めることは大きなテーマだ。予算を各省庁が独自に要求すると、全体として最適なAI戦略にならない。省庁の壁を取り払わなければ失敗する。その意味で、首相の強いリーダーシップが最終的な司令塔になる。
―米IT大手のマイクロソフトが生成AIの事業拠点をアジアで初めて日本に置いた。
チャットGPTを利用する際、入力したデータは海外に送られる。例えば役所が答弁作成に利用する場合でも、データが海外へ送られることはあり得ない。(データを国内で管理する)「データ主権」などの観点から歓迎すべきだ。