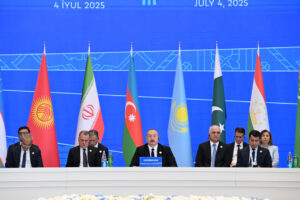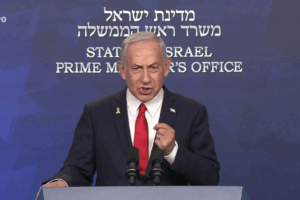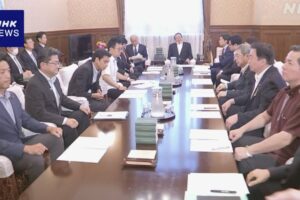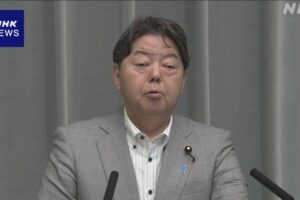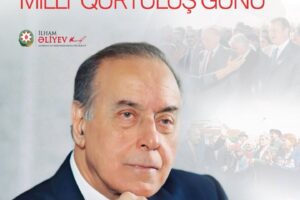東京, 10月22日, /AJMEDIA/
世界各国の日系人が一堂に会して交流を深める「海外日系人大会」が16~18日、東京都内で開かれた。江戸末期に海外渡航が解禁され、1868年に集団移民がハワイに渡ってから150年余りがたつ中、各地の日系人団体はコミュニティー存続への危機感を募らせる。一方、政府は日系人を、主な移民先だった中南米諸国との外交面で日本に貢献し得る重要な「人的資産」と捉え、連携に本腰を入れ始めている。
◇進む日本語離れ
コロナ禍を経て4年ぶりに対面開催された大会には、17カ国から約180人が参加した。ブラジル日本文化福祉協会の石川レナト会長は講演で、ブラジルにある約400の日系団体の4分の1が存続の問題に直面していると指摘。「ベテランの経験と若者の才能、エネルギーを組み合わせることで、団体が発展し長続きしていく」と訴えた。
2002年に250万人と推定されていた世界の日系人は、今では400万人に増加。ただ、世代交代に伴い日本語を話さない人が増え、今後も日系社会のアイデンティティーを維持できるかが危惧されている。
外務省が18~22年にブラジルやペルーなど中南米13カ国の若手日系人を対象に行った調査では、日本語の語学力について「初級レベル」以下と自己評価した人は8割で、このうち「全くできない」が半数超。一方、9割が自身を日系人と意識し、ほぼ全員が日本に好印象を持っていた。
外務省は「現地で一定の信頼を勝ち得た日系人の存在は、日本の中南米外交に資する」(関係者)と考える。今年1月には中南米の若手日系人を日本に招いたり、現地の日本関連イベントを支援したりするための「中南米日系社会連携推進室」を新設し、関係強化に乗り出した。
◇中国に対抗
こうした動きの背景には、経済力をてこに中南米で影響力を強める中国の存在がある。中国主導の巨大経済圏構想「一帯一路」にも中南米から20カ国超が参加。3月にはホンジュラスが台湾と断交し中国と国交を結んだ。
米政府が中央情報局(CIA)などを通じて政治や経済を牛耳り、かつては「米国の裏庭」と言われた中南米だが、キューバやベネズエラなど反米左派の国以外にも米国離れの動きが広がる。昨年6月にロサンゼルスで開かれた米州首脳会議は、メキシコやホンジュラスを含む多くの国の首脳が欠席した。日本政府関係者は「親中国で反米だから『反日』とはならないようにしなければならない。日系人はその点でも重要な人的資産だ」と強調した。