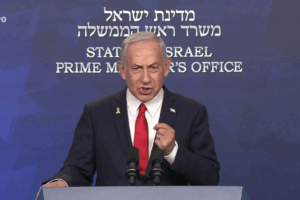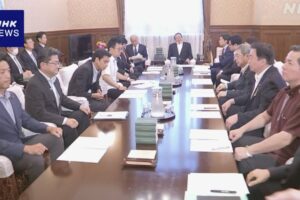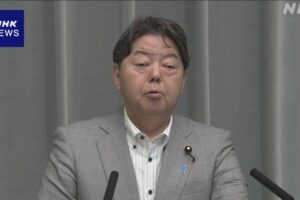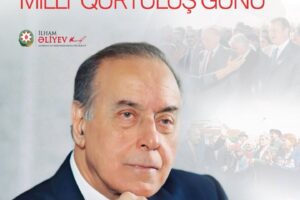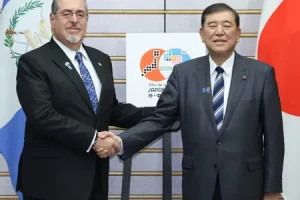東京, 11月27日, /AJMEDIA/
24日に総務省が公表した去年1年分の政治資金収支報告書について、NHKがインターネットに関連した政治活動への支出を独自に集計したところ、少なくとも2億6000万円余りにのぼり、動画制作やライブ配信のほか、リスク対策の支出など、項目は多岐にわたっています。
NHKは総務省が24日に公開した去年1年分の政治資金収支報告書のうち、国会議員関係の政治団体、706団体を対象に、インターネットに関連した政治活動への支出を独自に集計しました。
少なくとも全体の29%にあたる203の団体に関連の支出が確認され、支出額の合計は2億6468万円でした。
同じ条件で集計したおととし分の1億8333万円との比較で、大きく増加しています。
支出を項目別で見ると、
▽「Facebook」や「LINE」「YouTube」など、項目にSNSに関連した記載がある支出の総額は合わせて5068万円。
▽「動画制作費」や「ライブ配信費用」など、インターネットで政治活動を発信するためとみられる支出が4548万円でした。
このほか、
▽「ネット広告費」「ネット献金システム利用料金」などといった支出項目もみられました。
▽「インターネット対策費」の名目で、SNS上でのいわゆる「炎上」や、ひぼう中傷への対策などをしている企業に毎月60万円以上を支出している団体もありました。
インターネットを利用した選挙運動が解禁されてことしで10年になりますが、ウェブサイトやSNSの利用は選挙運動以外にも政治活動全般に広がり、政策の発信のほかリスクへの対策など、関連する支出が多岐に広がってきている状況がうかがえます。
ウェブサイトでの発信にも流行が
去年1年分の政治資金収支報告書を調べると、政治団体からの支出先として、インターネットを活用した政治活動のコンサルティングなどをする複数の企業の名前が確認されました。
このうち、ネットによる選挙運動のサポートをしている東京の会社には、ウェブサイトやSNSで有権者に政策を訴えたいという政治家や候補者からの相談が寄せられています。
ウェブサイトで活動を発信する政治家や候補者は以前よりも増えていますが、代表取締役の高畑卓さんが「今、政治家の間で特に流行している」と語るのは動画投稿サイト「ユーチューブ」を使った広告です。
文字情報や写真だけではなく、自分自身の表情や声で訴えを届けられるツールとして関心が高いということです。
高畑さんは「平均年齢が高い政治家の間では、今でも実名で利用されるフェイスブックが後援会のツールなどとして使われていますが、若い人や広く大多数の人にPRをしたいとなると、ユーチューブ。さらに若い層に訴えたいという人たちの間ではTikTokやインスタグラムの利用が増えています。全国歴代最年少の市長として、ことし話題になった兵庫県の芦屋市長も、TikTokで若者が関心を寄せそうなテーマを取り上げています」と話しました。
インターネット広告などを活用することで、ふだんはあまり政治や選挙に関心がない人、接点をつくりにくい若者層にも政策ごとにターゲットをしぼり訴えを届けることができるとしています。
会社が各地で主催しているネットの活用方法のセミナーには現職の議員や秘書、今後、立候補を考える人たちの参加希望があとを絶たないといい、11月、大阪で開かれたセミナーに参加していた和歌山県の市議会議員の男性は「それぞれのSNSに合わせた戦略を知ることができて、とても参考になりました。今後の選挙では選挙カーだけに頼らずに、ネットをさらに積極的に活用していきたい」と話していました。
ネット使った選挙運動 解禁から10年 若者は?
インターネットを使った選挙運動が解禁されて、ことしで10年。
若者の投票率は衆議院選挙、参議院選挙ともにほぼ横ばいの状況になっています。
千葉大学で、若者の政治参加に関心を持つ学生たちの議論を聞くと、
『選挙に行くことは、若者の中では学業やサークル、アルバイトと比べて優先度が低い』とか
『ネットで訴えられても、若い世代と政治家が持っている論点がそもそもずれていて、関心が沸きづらい』
といった意見が出た一方、
『SNSによって、政治の情報に触れる機会そのものは明らかに増えているし、若者が政治に関心が無いわけではないと思う。ただ、リアルの世界で政治の話をすると避けられる雰囲気を感じる』といった意見もありました。
また、『政治家がSNSで有権者からの要望や質問に丁寧に返信しているのを見て、政策への思いなどを理解することができた』といった声も聞かれました。
千葉大学大学院社会科学研究院の関谷昇教授は「さまざまなツールを使って政治家や候補者が情報を伝えるようになっているが、政治の側が設定する課題と、有権者が感じている課題が十分に呼応していないため、有権者にどれほどの形で響いているかは“道半ば”という印象だ」と話しました。
関谷教授は「海外では政治活動や選挙へのインターネットの活用がさらに広がっていて、若者の政治参加への自覚を高め、政治のすそ野を広げている」と述べる一方、課題も指摘していて、「ネットは分断を進める側面もあり、欧米ではポピュリズムで対立を浮き彫りにさせて、政治的な求心力を高めるための道具にされているケースもある。どうしても情報や議論が限定されてしまう部分があるので、発信する側も、受け止める側も、ネット空間だけでなく、リアルな現場の状況と合わせて多角的に考えることが必要だ」としています。