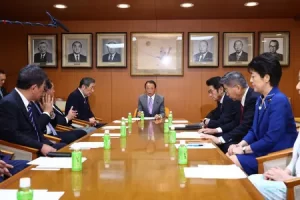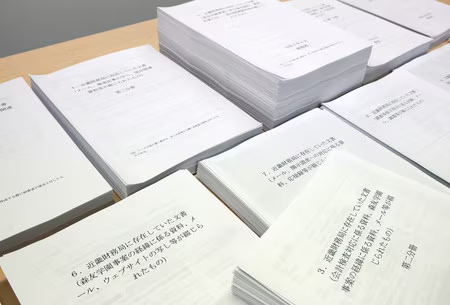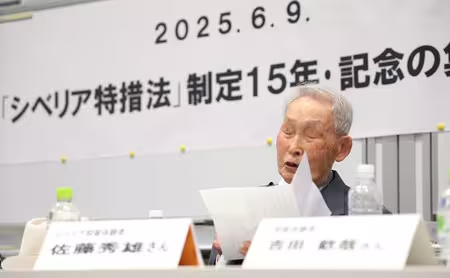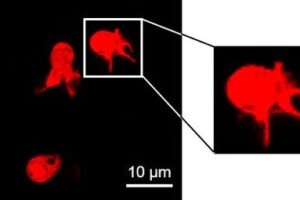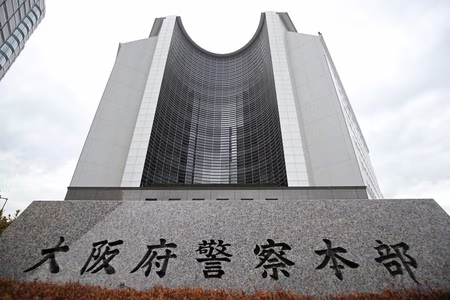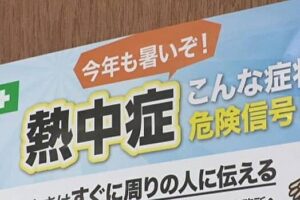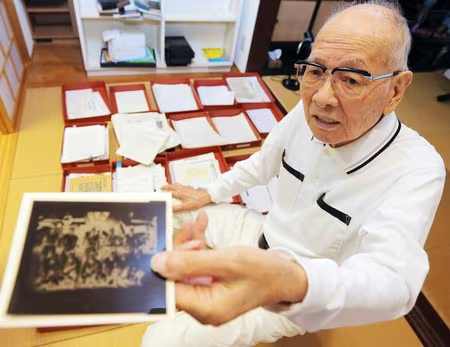東京, 5月6日, /AJMEDIA/
沖縄・宮古島周辺で起きた陸上自衛隊のヘリコプター事故は、6日で発生から1カ月。陸自は海底から機体を引き揚げ、フライトレコーダーを回収し、機体番号から事故機と断定した。今後詳しく調べるが、レコーダー解析などによる原因究明には時間がかかる見通しだ。
第8師団長(当時)の坂本雄一陸将ら10人が乗ったヘリは、離陸10分後に宮古島北西の洋上でレーダーから消失。機体は1週間後、水深106メートルの海底で見つかった。これまで坂本陸将を含む6人の遺体が収容されたが、4人が不明のままだ。
民間船で引き揚げた機体は、激しく損傷していた。陸自などによると、尾翼部が座席のあるキャビンに乗るようにして折れ、操縦席付近も壊れて外装が剥がれていた。海底にほぼ同じ形で沈んでいたという。
ただ、各部分は完全に破断しておらず、尾翼部は原形を保持。機体両脇にある着脱式の燃料タンクも一つは着いたまま残っていた。タンクは外れやすく、もう一つは割れて流されていたことから、機体は傾いた状態で落下した可能性がある。陸自は機体を熊本県の高遊原分屯地に運び、各部の破損状況などを調べる。
ヘリの発見場所は、消失地点から北に約4キロ離れていた。機体と破片は集中して見つかったため、流されたのではなく、発見場所近くに落下したとの見方が強まっている。
消失地点と発見場所はヘリの速度なら1分余りの距離で、レーダーに映らない低い高度を飛んだ可能性がある。ただ、なぜ緊急通報など非常時対応ができなかったかは不明だ。詳しい飛行状況や機内音声を記録したフライトレコーダーの解析には数カ月かかるという。
事故では、レコーダーの位置を告げる発信機や不時着時に機体を浮かせるフロートが未搭載で、機体が海上の事故に不十分な仕様だったことも明らかになった。陸自は南西諸島での運用を強化しており、幹部を一度に失った第8師団の立て直しとともに、こうした機材の見直しについても検討を始めている。