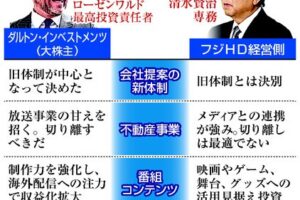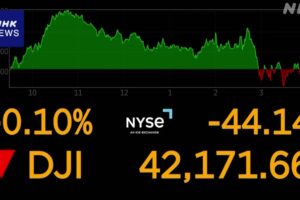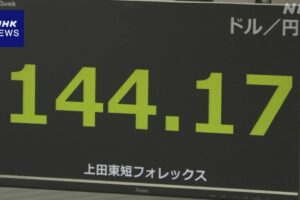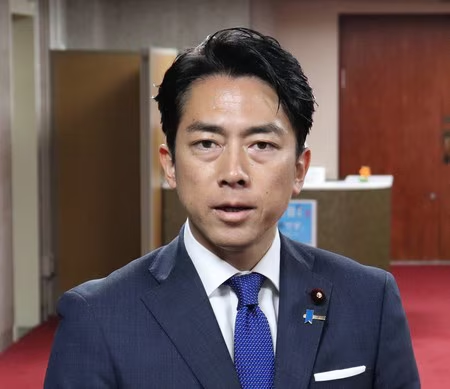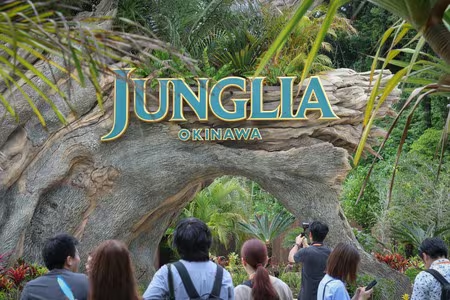東京, 6月14日, /AJMEDIA/
岸田政権が掲げる「異次元の少子化対策」の実現に向け、政府が決定した「こども未来戦略方針」では、児童手当の拡充や保育サービスの充実などを打ち出した。しかし、安定財源の確保が大きな課題として積み残されており、今回の対策により危機的な少子化に歯止めをかけることができるかどうかも不透明だ。
児童手当拡充でも負担増? 扶養控除見直し案浮上―こども未来戦略方針
「2022年の合計特殊出生率、過去最低の1.26」「年間出生数、初の80万人割れ」―。戦略方針が検討されていた今月2日、厚生労働省は衝撃的な統計を発表した。「30年代に入るまでが少子化トレンドを反転できるラストチャンス」としてきた岸田文雄首相の危機感が数字となって表れた形だ。
危機克服に向けた戦略方針の柱の一つが児童手当の拡充だ。所得制限を撤廃し、第3子以降への加算なども拡大する。一方、首相は増税を否定し、歳出改革などにより捻出する方針を強調。財源をひねり出す上での「痛み」は明確にしていない。
これに対し、自民党内からは「歳出削減の余地はない」とけん制する声が続出。高齢化の進展で社会保障費の拡大が続く中、少子化対策に必要な財源をどれだけ捻出できるかは見通せない。
児童手当の内容にも懐疑的な見方がある。日本総研の藤波匠上席主任研究員は「多子世帯支援の増額より第1子を出産する前の人への支援を拡充すべきだ」と指摘する。
戦略方針ではまた、妊娠から出産への切れ目ない支援や奨学金制度の充実による教育費の負担軽減、男性の育児休業取得率の引き上げを通じた共働きの推進など、子育てしやすい環境の整備に向けた幅広いメニューをそろえた。藤波氏は「経済成長や雇用の安定、所得アップを通じ、若者が安心できる豊かな社会にしなければいけない」とし、若年層の所得向上をポイントに挙げる。
ただ、こうした改革の実現には中小企業を含めた社会全体の意識改革が不可欠となる。戦略方針を絵に描いた餅にしないため、政府には実現に向けた各方面への働き掛けが求められる。